オペラに行って参りました-2017年(その3)
目次
| オッフェンバックはメロディメーカーである | 2017年5月28日 | 東京オペラプロデュース第100回定期公演「ラインの妖精」を聴く |
| 体力差 | 2017年6月10日 | 新国立劇場「ジークフリート」を聴く |
| 歌うのが楽しい!! | 2017年6月16日 | 「中森 美紀 ソプラノ・リサイタル ~My favorite songs~」を聴く |
| 日本語で上演するということ | 2017年6月24日 | 日生劇場「ラ・ボエーム」を聴く |
| 名曲にして難曲 | 2017年7月2日 | 藤原歌劇団共同公演「ノルマ」を聴く |
| 値頃感 | 2017年7月9日 | アーリードラーテ歌劇団「イル・トロヴァトーレ」を聴く |
| ベテランの魅力、中堅の力 | 2017年7月15日 | シゲキ宮松♪歌劇団旗揚げ公演「椿姫」を聴く |
| トラブルシューティング | 2017年7月23日 | Le voci「愛の妙薬」を聴く |
| テクニックと情感と | 2017年7月23日 | 南条年章オペラ研究室公演「カプレーティ家とモンテッキ家」を聴く |
| 神は細部に宿る | 2017年7月29日 | 東京二期会オペラ劇場「ばらの騎士」を聴く |
オペラに行って参りました。 過去の記録へのリンク
| 2017年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2017年 |
| 2016年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2016年 |
| 2015年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2015年 |
| 2014年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2014年 |
| 2013年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2013年 |
| 2012年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2012年 |
| 2011年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2011年 |
| 2010年 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | どくたーTのオペラベスト3 2010年 |
| 2009年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2009年 | |
| 2008年 | その1 | その2 | その3 | その4 | どくたーTのオペラベスト3 2008年 | |
| 2007年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2007年 | ||
| 2006年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2006年 | ||
| 2005年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2005年 | ||
| 2004年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2004年 | ||
| 2003年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2003年 | ||
| 2002年 | その1 | その2 | その3 | どくたーTのオペラベスト3 2002年 | ||
| 2001年 | その1 | その2 | どくたーTのオペラベスト3 2001年 | |||
| 2000年 | どくたーTのオペラベスト3 2000年 |
![]()
鑑賞日:2017年5月28日
入場料:B席 6000円 2F 2列29番
主催:東京オペラ・プロデュース合同会社
東京オペラ・プロデュース第100回記念公演
オペラ4幕、日本語字幕付ドイツ語上演
オッフェンバック作曲ラインの妖精」(Die Rheinnixen)
台本:シャルル・ニュイテル/ジャック・オッフェンバック
日本初演
会場:新国立劇場中劇場
スタッフ
| 指 揮 | : | 飯坂 純 | 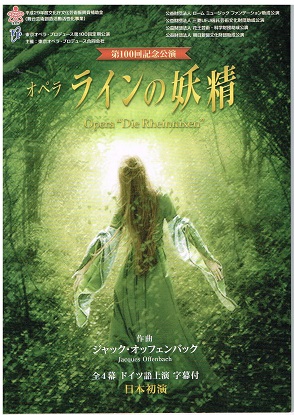 |
| 管弦楽 | : | 東京オペラ・フィルハーモニック管弦楽団 | |
| 合 唱 | : | 東京オペラ・プロデュース合唱団 | |
| 合唱指揮 | : | 中橋 健太郎左衛門 | |
| 演 出 | : | 八木 清市 | |
| 美 術 | : | 土屋 茂昭 | |
| 衣 裳 | : | 清水 崇子 | |
| 照 明 | : | 成瀬 一裕 | |
| ヘア・メイク | : | 星野 安子 | |
| 振 付 | : | 中原 麻里 | |
| 舞台監督 | : | 佐川 明紀 |
出 演
| アルムガード | : | 松尾 祐実菜 |
| コンラート | : | 米谷 毅彦 |
| ヘドヴィッヒ | : | 前坂 美希 |
| フランツ | : | 上原 正敏 |
| ゴットフリート | : | 佐藤 泰弘 |
| 妖精 | : | 二宮 望実 |
| 農夫 | : | 白井 和之 |
| 兵士1 | : | 内田 吉則 |
| 兵士2 | : | 奥山 晋也 |
| 妖精バレエダンサー | : | 森本 由布子 |
感 想
オッフェンバックはメロディーメーカーである-東京オペラ・プロデュース第100回定期公演「ラインの妖精」を聴く。
東京オペラ・プロデュースは、1975年7月、ビゼー「ミラクル博士」及びラヴェル「スペインの時」の旗揚げ公演以来、43年間で遂に100回の公演を達成したそうで、まことにおめでとうございます。東京オペラ・プロデュースはもともと前代表松尾洋さんの個人的な活動で始まったそうですが、松尾さんが亡くなった後も、奥様の松尾史子さんが引き継ぎ、財政的には非常に苦しい中、活動の幅を広げられ、今日に至ったこと、誠に素晴らしいことと思います。また、東京オペラ・プロデュースは、日本初演物が多く、そういうマイナーな作品はとりわけ集客が難しいと思いますが、そういう難しさの中続けてこられたことも、特に称賛したいところです。
私自身は、第62回公演ロッシーニ「オテロ」が最初の鑑賞で、それ以降は、ほぼ毎回(全部ではありません)聴いておりますが、それが唯一の鑑賞機会という作品が非常に多く、いつも大変ありがたく思っています。
日本初演物にアイデンティティのある東京オペラ・プロデュースだからこそ、100回記念公演で取り上げたものもかなりの珍品オペラになりました。オッフェンバックの「ラインの妖精」です。
オッフェンバックといえば「地獄のオルフェ」で代表されるオペレッタの作曲家であり、オペラ作品は未完の「ホフマン物語」が唯一である、というのが、21世紀の初めぐらいまでの常識だったと思いますが、実際はこの「ラインの妖精」という作品があったそうです。ウィーンの宮廷歌劇場からの依頼で書かれた本格的なオペラで、作曲家の意図通りに演奏すると4時間はかかるという大作なのだそうですが、諸事情で初演時にはほぼ半分の2時間規模にカットされ、その後10回ほど演奏されたそうですが、以降楽譜は出版されず、演奏されることもなく21世紀に至ったそうで、蘇演が2002年7月、その後何か所かで演奏されたそうですが、今回の東京オペラ・プロデュースの上演は蘇演以来、世界で6回目か7回目の上演になるのだそうです。
聴いて思ったのは、やっぱりオッフェンバックだな、ということです。確かにロマンティック・オペラなのですが、音楽的にフランス風洒脱さに満ちています。出演者に声の強さは求められるのですが、同時代のワーグナーのようなねっとりした味わいではないと思います。音楽が洒落ていて美しい。ロッシーニはオッフェンバックのことを「フランスのモーツァルト」と呼んだそうですが、その言葉が嘘でないことが」この作品を聴くとよく分かります。また、初聴の曲は、集中力が続かないことがしばしばあるのですが、今回はそんなことは全くなく、最初から最後まで楽しく聴くことができました。これは美しいメロディーがこれでもか、というぐらい続けて出るところが関係するのだと思います。
また、「ラインの妖精」が死蔵された後、そのモチーフは「ホフマン物語」に転用されており、その一番特徴的なのは「ホフマンの舟歌」のメロディです。このメロディは「ラインの妖精」の基本のモチーフで、「序曲」や第三幕の妖精たちの合唱で使用されるほか、断片的にはほかの部分でも聴こえてきます。
さて演奏ですが、総じて立派。まずダメ出しを最初にしておくと、東京オペラ・フィルの演奏は結構雑。ドイツロマン派を意識した音楽ということでホルンが活躍するのですが、ホルンは上手とは言えない感じです。またホルン以外でも金管楽器の活躍が多いですが、全体的にパッとしなかったように思います。
歌手ですが、最も安定感があったのが米谷毅彦のコンラート。米谷は最近裏切られたことのないバリトンでいつ聴いても素敵なのですが、 今回も例外ではなかったです。アンサンブルでもアリアでも安定した息遣いと声の強さで表情、表現ともよく研究しているな、ということを感じさせるもので、大いに感心いたしました。Bravoです。
前原美希ののヘドヴィッヒも素敵です。東京オペラ・プロデュース以外では聴いたことがない方ですが、密度が終始一貫していて、ドラマティックな表情の出し方などよく検討されているな、という印象。母親役の悲しみの表現なども非常に共感できるものでした。
アルムガード役の松尾祐実菜。初めて聴く方かと思いきや、松尾香世子なのですね。松尾は東京オペラ・プロデュースで25年以上歌っているベテランで、素晴らしいコロラトゥーラ・ソプラノですが、若いころと比較すると声の力は今一つ弱い感じはしますが、技術に衰えを感じさせるものはなく、主役としての華やかさを見せてくれたのではないかと思います。
上原正敏のフランツは非常に若々しいテノール声で頑張っていると思いますが、所々室しているな、と感じるところがありました。佐藤泰弘のゴッドフリード。健闘はされていましたが、音程の安定感が今一つだったように思います(もちろん、聴き手は初聴なので単純な印象論であり、正確に歌われていたのかもしれません)。二宮望実の妖精は一曲だけの歌唱ですが、とても印象的で素敵でした。
総じて良く練習されていますし、東京オペラ・プロデュースの第100回記念演奏会を盛り上げようという意思が出演者一同みなぎっていたのではないかと思います。カットもあったそうですが、休憩なしの実演奏時間が3時間20分、退屈せずに聴きとおせたのは、メロディーメーカーオッフェンバックの才能と、出演者の頑張りの相乗効果だったと思います。
![]()
鑑賞日:2017年6月10日
入場料:C席 7776円 4F 3列 39番
主催:新国立劇場
新国立劇場公演
全3幕、字幕付原語(ドイツ語)上演
ワーグナー作曲楽劇「ニーベルングの指環」第二夜「ジークフリード」("Der
Ring des Nibelungen" Zweiter Tag Siegfried)
台本:リヒャルト・ワーグナー
会場 新国立劇場オペラパレス
スタッフ
| 指揮 | : | 飯守 泰次郎 |
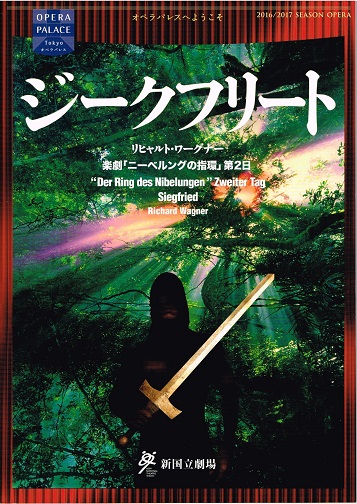 |
| オーケストラ | : | 東京交響楽団 | |
| 演出 | : | ゲッツ・フリードリヒ | |
| 美術・衣裳 | : | ゴッドフリート・ピルツ | |
| 照明 | : | キンモ・ルスケラ | |
| 演出監修 | : | アンナ・ケロ | |
| 演出補 | : | キム・アンベレラ | |
| 音楽ヘッドコーチ | : | 石坂 宏 | |
| 舞台監督 | : | 村田 健輔 | |
| 芸術監督 | : | 飯守 泰次郎 |
出 演
| ジークフリード | :ステファン・グールド |
| ミーメ | :アンドレアス・コンラッド |
| さすらい人 | :グリア・グリムスレイ |
| アリベルヒ | :トーマス・ガゼリ |
| ファーフナー | :クリスティアン・ヒューブナー |
| エルダ | :クリスタ・マイヤー |
| ブリュンヒルデ | :リカルダ・メルベート |
| 森の小鳥(黄) | :鵜木 絵里 |
| 森の小鳥(白) | :吉原 圭子 |
| 森の小鳥(赤) | :安井 陽子 |
| 森の小鳥(緑) | :九嶋 香奈枝 |
| 森の小鳥(青)(バレエ) | :奥田 花純(新国立劇場バレエ団) |
感 想
体力差-新国立劇場「ジークフリード」を聴く
14時に開演され、終演したのが19時40分過ぎ。5時間40分の長丁場は聴くほうもそれなりの覚悟が必要です。今回4階3列の席だったのですが、この椅子が少し壊れかけていて、座面が少し前に傾いている。そのせいもあって、第三幕辺りになると少し腰がだるくなり始めます。聴き手ですらそうですから、演奏する方はもっと大変でしょう。それを痛切に感じたのがオーケストラ。
今回のオーケストラは東京交響楽団でしたが、演奏の精度が第1幕と第3幕とでは全然違う。東京交響楽団は管楽器の上手なオーケストラという印象があるのですが、第一幕はその得意の管楽器が本当に上手。木管も金管も惚れ惚れするような音を出してくれる。ワーグナーの楽劇はもちろん歌手も大切ですが、オーケストラの咆哮あってこそですから。第一幕や第二幕の演奏を聴いていると、ワーグナーを聴く醍醐味がとてもよく味わえます。しかしながら、三幕は確実に演奏の精度が落ちました。金管のファンファーレはへなちょこになっていましたし、弦のアインザッツだって乱れ始める。やっぱりオーケストラも第三幕になると集中力が続かなくなるのでしょうね。それはそうだと思います。通常のコンサート三回分の演奏を一日でやるのですから大変でないはずがない。
日本のワーグナー指揮者として最初に指折られる飯守泰次郎。彼の目指す音楽は、昨年の「ワルキューレ」の延長線上にある音楽でしょう。明晰で澱みのない音楽。それは前半は確実に達成されていましたし、彼の指揮自身は緩むことなく最後まで突き進んだと思います。ただ、第三幕の第三場、ジークフリートとブリュンヒルデの二重唱のオーケストラは、もっと官能的に響いたほうがよかったのではないか、という気がします。後述のようにこの場面、歌手がものすごくよかったので、オーケストラも歌手に寄り添って、もっと官能的に響けば印象がさらに良くなったような気がします。
歌手陣ですが、ジークフリード役のステファン・グールド、ミーメ役のアンドレアス・コンラッドが特によく、クリスタ・マイヤーのエルダ、リカルダ・メルベートのブリュンヒルデもよかったです。その他の外人勢もみなその役目を果たしており、立派だったと申し上げられます。
ステファン・グールド。圧倒的に素晴らしいヘルデンテノール。一昨年、「ラインの黄金」でのローゲ、昨年の「ワルキューレ」でのジークムントと、ほんとうに素晴らしい歌で、今回のジークフリートも期待されたわけですが、その期待を裏切らない名唱。声に力があるのは当然なのですが、更に美しい。そして、場面場面での声の切り替え方もまた見事です。「ジークフリート」は「怖いもの」を知らない自然児ジークフリートの成長のオペラともいえる訳ですが、最初の傲慢なやんちゃな雰囲気から第三幕第三場の愛の二重唱に至るまでその声が場面の特徴によりそうさまは見事としか申し上げようがありません。ことに終幕の愛の二重唱はそれまであれだけ歌っているのに、まだあれだけ柔らかい声はフォルテで響いてくる。こういうところに、日本人との体力差を感じてしまいます。また、そうできるところ、本物のヘルデン・テノールの魅力を感じさせられました。感服です。
アンドレアス・コンラッドも素晴らしかったと思います。テノールですが第一幕はジークフリートと対照的な声で特徴を際立たせる必要がある。そこが本当にうまい。ミーメの小心者的小狡さが見事に表現されていていました。ミーメが上手だったからジークフリードが更に輝いた、という部分が確実にあると思います。キャラクター・テノールの役ですし、コンラッドもキャラクター・テノール的に表現していたと思うのですが、声そのものはかなり美しく、美声テノール二人そろった感じも楽しめました。
グリムスレイのさすらい人。よかったと思います。低音担当ですからジークフリードやミーメのような華やかさがないのは当然ですが、その中でしっかり歌いあげていた印象。グリムスレイは、昨年10月の「ワルキューレ」ではヴォータンを歌って、もう一つ歌に透明感が欲しいなと思ったのですが、今回はそういう気持ちにはなりませんでした。たぶん「ワルキューレ」におけるヴォータンの立ち位置と「ジークフリード」における「さすらい人」の立ち位置が違っていて、「ワルキューレ」では当事者であるのに対し、「ジークフリード」では部外者である、ということが関係しているのでしょう。グリムスレイは部外者であることの焦燥感のようなもの。また部外者であるための隔靴掻痒な感じの表現がすごくよかったと思います。
他の男声脇役陣もそれぞれ立派な声で、自分の役割を果たしていました。
女声陣では、エルダ、ブリュンヒルデともに立派な歌唱。「ジークフリード」は男のオペラで、女声が活躍するのは、第三幕の第一場と三場だけ(森の小鳥は第二幕で出てきますけど)なので、ジークフリードやミーメとは大変さが全然違うのですが、その中でそれぞれの役目をしっかり果たしていました。クリスタ・マイヤーの低音の迫力も、メルベートの力強い高音もさすがだったと思います。森の小鳥は、本来一人で歌うところを演出の関係で四人で分担。木に留まって歌わなければいけないので、体勢的にはたいへんですが、音楽的にはごく普通でした。
舞台に関しては、今回の「リング」の一貫した特徴ですが、台本によく対応した平明な舞台。「ラインの黄金」、「ワルキューレ」の時も申し上げたのですが、「指環」四部作は、よく知られていると言っても決して分かりやすいストーリーの作品ではないので、ストーリーにほぼ忠実な舞台演出は、聴き手を助けてくれると思いました。
以上、オーケストラの疲れはあったものの、音楽・舞台共に水準の高い演奏であり、
「神々の黄昏」への期待をしっかりつなぐ演奏だったと申し上げられます。
![]()
鑑賞日:2017年6月16日
入場料:自由席:2500円
中森 美紀 ソプラノ・リサイタル ~My favorite songs~
会場:フォーシーズン志木 ふれあいプラザ
出 演
| ソプラノ | : | 中森 美紀 |
| ピアノ | : | 山中 優 |
プログラム
| 作曲者名 | 作品名 | 曲名 |
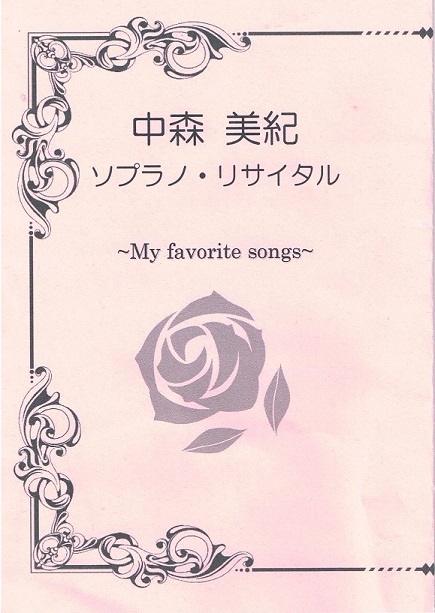 |
| ロッシーニ | 「音楽の夜会」より第1曲 | 約束 | |
| ベッリーニ | 「3つのアリエッタ」より第1曲 | 激しい希求 | |
| トスティ | 夢 | ||
| クルティス | 勿忘草 | ||
| モーツァルト | 歌劇「フィガロの結婚」よりスザンナのアリア | とうとう嬉しい時が来た | |
| グノー | 歌劇「ファウスト」よりマルガレーテのアリア | 宝石の歌 | |
| 休憩 | |||
| ロウ | ミュージカル「マイ・フェア・レディ」よりイライザのナンバー | 踊りあかそう | |
| ストラウス | ミュージカル「アニー」よりアニーなどのナンバー | TOMORROW | |
| BEGIN | 涙そうそう | ||
| いずみたく | 見上げてごらん夜の星を | ||
| プッチーニ | 歌劇「ラ・ボエーム」よりムゼッタのワルツ | 私が街を歩くと | |
| グノー | 歌劇「ロメオとジュリエット」よりジュリエットのワルツ | 私は夢に生きたい | |
| アンコール | |||
| 菅野 よう子 | 花は咲く | ||
感 想
歌うのが楽しい!!-中森美紀 ソプラノ・リサイタル ~My favorate songs~を聴く
藤原歌劇団所属のソプラノ中森美紀による自主コンサート。手作り感満載の楽しいコンサートでした。会場は志木駅前の丸井の8階で店の中を突っ切って進む感じ。音楽専用会場ではなく、たぶん普段はカルチャーセンター等で使用されているところではないかと思います。天井も低く、響きもデッドで決して歌いやすい会場ではないと思いますが、声が割れて聴こえるようなことはありませんでした。
プログラムの前半は、彼女の声がソプラノ・リリコ・レジェーロであることを前提にした選曲、後半は彼女が今歌える、あるいは歌いたい曲でまとめたプログラムで、自分の今を前提にした選曲でしょうから特に悪いものはなかったのですが、全体的に見れば後半のほうがよかったと思います。
中森を聴くのは初めての経験です。彼女は声に艶と粘りのある方で、高音は伸びるのですが、すっきりと伸びるという感じではありません。したがって軽やかに歌う曲よりもしっかり歌う曲のほうが似合っている感じがしました。そういう意味ではロッシーニやモーツァルトよりもグノーやプッチーニの方があっているのでしょう。また、低音はあまり得意ではないようで、「踊りあかそう」の低い部分は、高いところのようには上手くいっていなかった感じです。
その他テクニカルなミスは散見されましたが、「歌いたい歌を歌ってやるんだ」という意気込みと、「歌いたい歌を歌っているんだ」という幸福感が歌唱から満ち溢れていて、そこが一番良かったことだと思います。終始にこにこされていて、「歌うって楽しいことなんだよね」ということを観客に伝え続けるような歌でした。
そういった全体をひっくるめてよかったのは、前半は「勿忘草」と「宝石の歌」、後半は日本語の歌謡曲と「私は夢に生きたい」だったと思います。日本語の曲は歌唱技術的に言えばかなり易しく、オペラ歌手にとっては当然の歌唱なのでしょうが、あのようにしっかりと歌われると非常に魅力的です。「宝石の歌」は彼女の声にまさにぴったり。技術的にはミスもあったのですが、声と表現のバランスがうまく取れていて見事でした。「私は夢に生きたい」は、歌いこんできた自信が音楽にあり、そこが素敵でした。
「中森美紀ソプラノリサイタル」TOPに戻る
本ページTOPに戻る
![]()
鑑賞日:2017年6月24日
入場料:B席 5000円 2F G列 17番
主催:公益財団法人ニッセイ文化振興財団(日生劇場)
NISSAY OPERA 2017
全4幕、字幕付日本語訳詞上演
プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」(La Boheme)
台本:ジュゼッペ・ジャコーザ/ルイージ・イッリカ
日本語翻訳:宮本益光
会場 日生劇場
スタッフ
| 指揮 | : | 園田 隆一郎 |
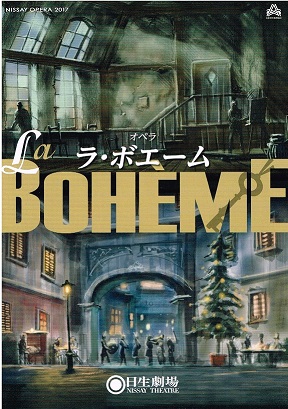 |
| オーケストラ | : | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | |
| 合唱 | : | C.ヴィレッジシンガーズ | |
| 合唱指導 | : | 田中 信昭 | |
| 児童合唱 | : | パピーコーラスクラブ | |
| 児童合唱指導 | : | 籾山 真紀子 | |
| 演出 | : | 伊香 修吾 | |
| 美術 | : | 二村 周作 | |
| 照明 | : | 斎藤 茂男 | |
| 衣裳 | : | 十川 ヒロコ | |
| 演出助手 | : | 手塚 優子 | |
| 舞台監督 | : | 幸泉 浩司 |
出 演
| ミミ | :北原 瑠美 |
| ロドルフォ | :樋口 達哉 |
| マルチェッロ | :桝 貴志 |
| ムゼッタ | :高橋 絵理 |
| ショナール | :近藤 圭 |
| コッリーネ | :三戸 大久 |
| ベノア | :押見 春喜 |
| アルチンドロ | :小田桐 貴樹 |
| パルピニョール | :青栁 貴夫 |
感 想
日本語で上演するということ-NISSAY OPERA 2017「ラ・ボエーム」を聴く
イタリアオペラを日本語で上演することはあまり良いことだと思っていません。私がオペラを聴き始めた頃は日本語訳詞上演がまだあったころですが、日本語が何を言っているのか本当に分からない。これは凄いフラストレーションです。その後藤原歌劇団が字幕システムを導入し、外国オペラを日本語で上演することは稀になりましたが、これは、「オリジナルを演奏すべきである」という原則論のほかに、日本語で演奏する方が分かりにくくなる、という現実が関係しているように思います。オペレッタは今も日本語で上演されることが多いですが、「こうもり」、「メリー・ウィドウ」のようなかなり演奏されているものは、日本語訳もこなれていますが、滅多にやらないものを日本語でやると、やっぱりぐちゃぐちゃです。
でも日生劇場はオペラも日本語で上演したほうが裾野が広がると考えたようです。そのため、今回の舞台を作るにあたり、宮本益光に白羽の矢を立てて、日本語台本をお願いしたそうです。宮本は二期会を代表するバリトン歌手ですが、オペラの日本語訳詞の創作をライフワークとしていて、既に何作品も発表しています。ちなみに私も二、三聴いたことがあります。その宮本が作成した「ボエーム」の日本語訳、正直申し上げて思った以上の出来栄え。かなり分かりやすい。更に申し上げるならば第4幕の後半は、オペラでありながら、オペラでないような普通のドラマを見ているような気に一瞬なりました。これは舞台の内容が言葉に昇華して、観客の心に入り込んだということのように思います。大きくまとめれば成功だった、と申し上げてよいと思います。
しかしながら、それでも私は原語上演を支持します。確かに舞台を見るという観点で日本語はいいけど、音楽とのつながりの点で、イタリア語と日本語は全く異質です。まずアクセントの位置が違いますし、一つの単語の音節の構成も違う。また同じ情報を提供しようと思うと、日本語の方がたくさん単語を言わなければいけないという問題もあります。そういうところ、歌手たちは多分楽譜の指示とは違ったことをやって、舞台として見せる工夫をしているようでした。その結果として抒情的な表情の強いシーンはそれほど違和感がないのですが、男四人、すなわちロドルフォ、マルチェッロ、ショナール、コッリーネが重なる四重唱の部分はかなり乱暴に聴こえてしまうきらいがありました。これは多分、歌手たちがテンションを上げて、日本語で口を回しすぎて、音楽的表情を壊してしまった、ということではないかと思います。またかなり工夫はされていましたが、音価と言葉が合わないところが何か所かあり、全てが解決できていたわけではない、ということは申し上げてよいと思います。
結局のところ日本語でやらなければ考えなくてよいことを日本語でやったがゆえに苦労をして、演奏としても原語でやった方がもっと良い演奏になったのではないかという気がする訳です。
しかしながら、わたしは今回のボエーム、良い演奏だったと思っています。私はボエームはもちろん何回も舞台を見ているのですが、正直なところ満足できた、という演奏はあまりありません。今回は私の聴いたベストのボエームではないのですが、かなり上位のボエームです。これが原語でやれば音楽的な感動がもっと上がったのではないかという気がするのです。
まずオーケストラがよい。劇場の音響効果もかなり影響しているのでしょうが、オーケストラの音が生き生きとしています。指揮者の意図もあったのでしょうが、オーケストラの音に大げさに申し上げるならば青春の息吹を感じました。「ボエーム」のオーケストラパート、かなり緻密に書かれています。ですからオーケストラと歌手がお互いに引っ張り合いながら盛り上げられる作品なのだろうと思うのですが、多くの場合歌手の方が強く感じられることが多い。今回は日本語上演だったため、指揮者やオーケストラもそれを意識していて、歌手たちをフォローしようとして、少し前向きの演奏をされたのでしょう。それが功を奏した感じがします。指揮者の園田隆一郎を含めBraviです。
歌手陣に関してはまずミミとロドルフォがよかったです。ミミは実はなかなか満足できない役柄です。フレーニとか砂川涼子とかあるいは佐藤美枝子など感心したミミ歌いもいますが、なかなか感心できません。その中で本日の北原瑠美はかなり健闘していたと申し上げてよいと思います。声が中庸でずっと安定しているところが見事です。厚みの均整な声と申し上げたらよいのでしょうか。ミミという役柄のイメージによくあった声で、余裕のある歌い方の感じもよいと思いました。
ロドルフォの樋口達哉も見事です。樋口は二期会を代表するロドルフォ歌いと申し上げてよいと思うのですが、彼は得意な役柄では頑張りすぎて自滅してしまうことが時々あります。今回もそうなるのではないかと一抹の懸念があったのですが、それは全くの杞憂でした。今回は全体に丁寧な行き届いた歌唱で無理がなく、それでも「冷たい手」のハイCなど決めるところは決めるといった具合で、とても素敵な歌だったと思います。文句なしにBravoです。
あとよかったのは、ムゼッタの高橋絵理。高橋は以前と比較すると身体ができてきた感じで、音に深みが感じられました。ムゼッタは高音に伸びのある軽めの声の方がやる役柄ですが、高橋のように高音も響くけど声に厚みがあるという方が歌うと、ムゼッタという役柄の持っているパワーがより前面に押し出されるのだろうと思いました。素敵なムゼッタでした。
他の男声三役は、日本語の歌詞に翻弄されたのか、ちょっと落ち着かない感じで、歌も乱暴に聴こえました。若さの爆発を表現するためにはある程度荒いのは許されるのかもしれませんが、音楽的にはもう少し落ち着いて押さえた歌唱の方がアンサンブルが美しく響くと思いました。
今回の舞台は、伊香修吾の五島音楽賞研修成果発表という意味もあるのですが、演出はなかなか良かったと思います。冒頭、ミミのお墓の周りに集まってくる五人。ミミとの出会いと島では五人の共通した思い出として描かれます。だから、ミミの死と同時にすべてのセットは取り払われ、最初のお墓に五人がたたずむというもの。ミミの死を回想するという演出プランはよくあるもので、私も初めてではありません。しかし、最初にお墓を出し、最後にお墓をもってきて、その間の舞台装置の変換をこれほどのスピード感を持ってやるというのは見事だと申し上げてよいのではないでしょうか。また各幕ごとの舞台美術も非常に具象的でボエームというオペラにぴったりだったと思います。
![]()
主催:公益財団法人びわ湖ホール/公益財団法人ニッセイ文化振興財団/川崎市スポーツ・文化総合センター/公益財団法人日本オペラ振興会/公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団
藤原歌劇団共同制作公演
全2幕、字幕付日本語訳詞上演
ベッリーニ作曲「ノルマ」(Norma)
台本:フェリーチェ・ロマーニ
会場 日生劇場
スタッフ
| 指揮 | : | フランチェスコ・ランツィロッタ |
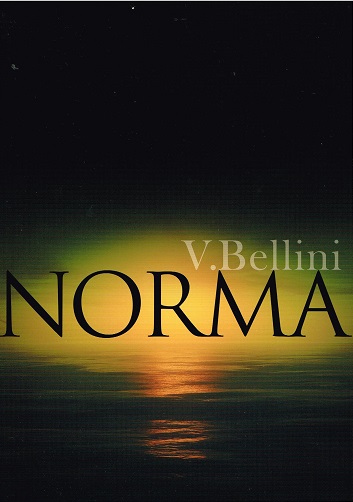 |
| オーケストラ | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |
| 合唱 | : | 藤原歌劇団合唱部/びわ湖ホール声楽アンサンブル | |
| 合唱指導 | : | 須藤 桂司 | |
| 演出 | : | 粟國 淳 | |
| 美術 | : | 横田 あつみ | |
| 照明 | : | 原中 治美 | |
| 衣裳 | : | 増田 恵美 | |
| 舞台監督 | : | 菅原 多敢弘 |
出 演
| ノルマ | :小川 里美 |
| アダルジーザ | :米谷 朋子 |
| ポリオーネ | :藤田 卓也 |
| オロヴィーゾ | :田中 大揮 |
| クロティルデ | :但馬 由香 |
| フラーヴィオ | :小笠原 一規 |
感 想
名曲にして難曲-藤原歌劇団共同制作公演「ノルマ」を聴く
今回日本オペラ振興会のご厚意で、ゲネプロを見せていただきました。ゲネプロは時間の関係で一幕の後半からだけだったのですが、それでも、今回のキャストで2回の演奏を聴くことができた訳です。その感想を一言で言えば本番は大変だな、ということに尽きます。
全般的に申し上げれば、小川里美はゲネプロよりも本番に本気を出してきてそれがうまく回っていた感じがします。田中大揮も同じです。一方、藤田卓也も米谷朋子もゲネプロの方が良かったと思います。本番は緊張して本来の力を出し切れなかった、と申し上げてよいのではないでしょうか。
小川里美は本番の方が良かったと申し上げましたが、「ノルマ」は小川向きの役ではないのではないかという気がしました。小川は中低音は安定していて素晴らしい声を持っている方ではありますが、高音は本来そこまで立派な方ではありません。更に申し上げればアジリダの切れ味も今一つのところがある。ノルマは要するに高音も低音もしっかり歌えて、それで技術的にもしっかりしたソプラノでないと太刀打ちできない役柄です。マリア・カラスが「一番難しい役はのノルマである」と言ったそうですが、カラスほどの不世出の大歌手をしてそう言わせるわけですから、小川のような高音の厳しい歌手にはちょっと太刀打ちできないのかもしれません。ハイDのアクートもなかったですし。
では小川の歌唱が悪かったか、と言えばそんなことは全然ありません。ベルカント的技巧という観点では今一つだと思いますが、その代わり、彼女は役柄をよく研究して本番に臨んでいたと思います。中低音は細かいところまでとても丁寧に歌っていましたし、ブレスの取り方などもとても丁寧でした。言葉と音価が一致して、柔らかい表情が見事だったと思います。第二幕が、第一幕で頑張りすぎたのか、ちょっと集中力が散漫になり始めていたようですが、小川としては今できることをしっかりやったノルマ役だった、と申し上げてよいと思います。
アダルジーザはある意味ノルマより大変な役柄です。一応メゾが歌うのが普通ですけど、ノルマよりも高いところで歌わなければいけないところが何度もあり、普通のメゾ歌手にはなかなか太刀打ちできないと思います。実は私はノルマは実演三度目なのですが、最初のノルマとアダルジーザはリッチャレッリと松本美和子でした。松本は当時の日本を代表するソプラノ・リリコ・スピントですが、多分リッチャレッリと声質が似ていてハモりやすいということを意識したキャスティングだったのではないでしょうか。その意味で今回の米谷朋子の選択は小川里美との声のバランスを考えていると思いますが、米谷の弱点も高音です。メゾの音域ではそこそこ立派な声をしていると思うのですが、高音部は声自体が金切り声ぽくなっていて、あまりよくありません。それでもゲネプロの時は肩に力が入っていなかったのか、重唱の表情などとても良かったのですが、本日はさほどではありませんでした。正確には、本番は上手くいっていなかった、と申し上げるべきでしょう。最も極端な例が、第二幕のノルマとの二重唱。ゲネプロの時は綺麗にハモッテいて本番すごく期待していたのですが、本番は結構ずれていたようで、あまり綺麗には響いていませんでした。
藤田卓也は元々美声ですし、ポリオーネという役にあっていると思います。登場のアリアはなかなか素敵でした。唯彼も本番で緊張していたのかもしれません。一幕フィナーレの三重唱はちょっと肩に力が入りすぎていたのか、ゲネプロ時よりも空回り感がありました。この一幕フィナーレの三重唱。ゲネプロの時は熱気はなかったけど綺麗にまとまっていて、これで熱気が加わったら凄いだろうなと思ったのですが、本番では熱気の加わった分アンサンブルとしてのコントロールが甘くなったということはあるかもしれません。
そんな訳で、今回一番よかったのはオロヴィーゾ役の田中大揮でしょう。彼は響きが充実していて落ち着いており、とても立派な父親役を務めていたと思います。
それ以外の脇役勢は小笠原一規が美声で素敵。但馬由香も自分の役目を果たしていたと思います。合唱の充実ぶりはいつもの如くです。
フランチェスコ・ランツィロッタ指揮の東京フィルハーモニー交響楽団はなかなか生々しい音でよかったと思います。日生劇場の広さと響きの感じによく合っていたということかもしれません。
粟國淳の演出は、オーソドックスでストーリーに即した分かり易いもの。私はノルマ実演3回目と書きましたが、1.2回目とも演奏会形式で、舞台を見るのは初めてです。このオペラは舞台を見なくても楽しめる作品ではあると思いますが、舞台があればその楽しみは拡大します。見ることができてよかったです。またほぼ15年ぶりで全曲を聴いたわけですが、ベッリーニの良さが詰まった最高傑作だと改めて思いました。
![]()
鑑賞日:2017年7月9日
入場料:S席 8500円 1F 8列 16番
主催:アーリドラーテ歌劇団
アーリドラーテ歌劇団第5回公演
全4幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演
ヴェルディ作曲「イル・トロヴァトーレ」(Il
Trovatore)
台本:サルヴァトーレ・カンマラーノ(補作:レオーネ・エマヌエーレ・バルダーレ)
会場 シアター1010
スタッフ
出 演
指揮
:
山島 達夫
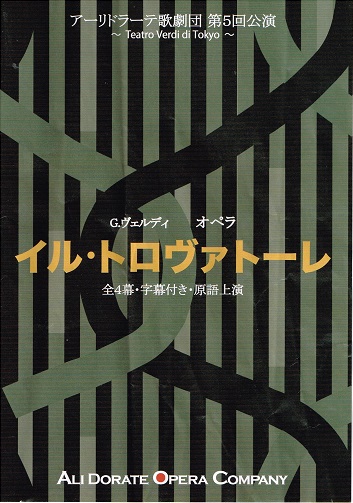
オーケストラ
:
テアトロ、ヴェルディ・トウキョウ・オーケストラ
合唱
:
ヒルズ・ロード・コーラス
合唱指導
:
大貫 浩史
演出
:
木澤 譲
照明
:
照井 晨一
舞台監督
:
石井 忍/渡辺 重明
マンリーコ
:小野 弘晴
レオノーラ
:石原 妙子
ルーナ伯爵
:野村 光洋
アズチェーナ
:二渡 加津子
フェルランド
:大澤 恒夫
ルイス
:明石 将岳
イネス
:田中 由佳
老ジプシー
:西崎 俊文
使者
:坂本 忠篤
感 想
値頃感-アーリドラーテ歌劇団第5回公演「イル・トロヴァトーレ」を聴く
最初チラシを見たときに思った感想は、「高いな」でした。S席8500円という値付けは、これが新国立劇場、二期会、藤原歌劇団であれば超お安いわけですが、SS席、S席、A席の3ランクしかない席構成での第2ランクの値段、かつ第三ランクのA席は全体の10%以下という中での8500円です。どれぐらいが妥当かといえば、2週間後にLe vociの「愛の妙薬」がモノクラスで4000円ですし、8月の荒川区民オペラは、5000円、3500円、2000円の3クラスです。このあたりがひとつの目安かな、という印象です。正直申し上げれば、大好きな「トロヴァトーレ」だったから出かけましたが、「椿姫」とかを上演したのであれば、行かなかったと思います。
こうは書きましたが、聴いて満足させていただけるのであれば、10000円ぐらい払うのは惜しくありません。しかし、今回の上演、8500円を払った価値を感じることはできませんでした。その責任は制作面にあると思います。まず劇場がよろしくない。「シアター1010」でオペラが上演できることは知っておりましたし、過去にも出かけたことがある訳ですが、ホールの音響がよくありません。変な響き方がして、音がまとまってこない印象があります。結果として、音楽的な魅力が減殺されました。これは非常に残念です。もう少し響きの適切なホールを選んで欲しかったな、というのがまず第一の苦情。
そして気に入らないのが演出。演出家は何かを考えてあの舞台にしたと思いますが、演出家の主張が全く見えない。舞台にカーテンを吊るして白い箱にし、そこに普段着にマフラーをまいた兵隊が出てきたり、喪服に赤いレインコートのレオノーラが出てくる。ほとんど小道具はなしで、「一応現代風にアレンジしました」という舞台。こういう舞台は作品によっては「あり」でしょう。でも「トロヴァトーレ」でありか?、と問われたらなしでしょう。そもそも論を申し上げれば、このお話は14世紀か15世紀のスペインが舞台です。主人公は「吟遊詩人」で、ヨーロッパではほぼ16世紀にはいなくなっています。すなわち、ヴェルディにとっても「時代劇」なのです。主人公も歌っている内容が「時代劇」で、現実に「火あぶり」もあれば、「チャンバラ」もある。これを現代に読み替えようとするなら、もっともっと工夫してもらわないといけません。自前のTシャツや綿パンを穿かれて、棒をもって「エイ・エイ・オー」とやられてもね、真実感も現実感もない。運動会の余興ではないのです。
音楽そのものは、いろいろと気に入らないところはありましたが、全体としてはまとまっていたと思います。
小野弘晴のマンリーコ。全体的にはそつなくまとめていたという印象です。ただ、この方高音になると喉声になる傾向があり、聴きにくくなります。高音が浮いてしまう印象です。これに重りをつけてもう一段押さえたところで歌っていただければ、もっと楽しめたのかな、と思いました。逆に高音を張らなくてよい重唱のシーンなどは抒情的な色合いがよく出ていてよかったと思います。
石原妙子のレオノーラ。声に迫力があり、声量も十分なリリコ・スピント。若い真直ぐな表現でよかったと思いますが、音が少し下がり気味の傾向があるようです。例えば「静かな夜」での上行音型ですが、最後はつじつまを合わせるのですが、そこに至るまでの中間音が本来の音よりも微妙に低い。また彼女だけが悪いわけではありませんが、重唱でハモるまでが、ちょっと時間がかかる印象。そのあたりの正確さは改善の余地があると見ました。また声質それ自身もわたくしの趣味とはちょっと違う感じです。そこが彼女の個性なのですから余計なお世話ですが、もう一つ響きを作る工夫をされていくとよいのにな、と思いました。そういった問題は感じられたにせよ、声そのものに力があるというのは凄い強みだと思います。今後の伸びに期待しましょう。
野村光洋のルーナ。よかったと思います。「君の微笑み」などは雰囲気がよく出ていたと思いますし、重唱部分でもしっかりしていた。ただこの方妙なところで引くんですよね。そういう歌い方もあるのかもしれませんが、もっとストレートに押された方がルーナ伯爵の立ち位置が見えるのかな、という気はしました。
二渡加津子のアズチェーナ巧いと思います。雰囲気もよく出ているし、高音も低音もしっかりしていた。このメンバーの中では一番のベテランで場数も踏んでいらっしゃると思いますが、それだけの経験値があるのでしょう。アズチェーナがどっしり控えているとこのオペラのおどろおどろしさが盛り上がります。その意味で二渡が歌ったことは凄くよかったと思うのですが、せっかくの重みを演出がスポイルした印象もまた強いです。おどろおどろしさがこのオペラの持ち味の一つだと思うのですが、それを見せないというのが演出の意図だったのでしょうか?
大澤恒夫のフェルランド。よかったです。今回のメンバーの歌唱の中で、実は一番いいなと思ったのは大澤の歌唱です。すっきりとしていて丁寧で、合唱を引っ張る部分は引っ張ってよかったです。
合唱は「ミゼレレ」のように裏で歌っている方が断然綺麗。演技をしながら歌うことに慣れていないように見受けられました。ことにテノールが今一つ。出が遅れることもありました。オーケストラは迫力のある音。全体バランスからすればもう少し落としてもよいのではないか、という声もあったのですが、わたしはオーケストラのこの迫力は支持してもよいのかなと思いました。山島達夫の指揮は自分のやりたいことをやらせているという印象の指揮。オーケストラは十分な推進力がありましたので、良かったのではないかと思います。
以上、「トロヴァトーレ」は、今年2回目で、4月に聴いた「江東オペラ」とは比較にならない素晴らしさでしたが、トータルの値頃感としては高かったのかな、というのが正直な印象です。
![]()
鑑賞日:2017年7月15日
入場料:自由席 5000円
主催:シゲキ宮松♪歌劇団
シゲキ宮松♪歌劇団旗揚げ公演
全3幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演
ヴェルディ作曲「椿姫」(La
Traviata)
原作:アレキサンドル・デュマ・フィス
台本:フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ
会場 セシオン杉並ホール
スタッフ
出 演
指揮
:
宮松 重紀
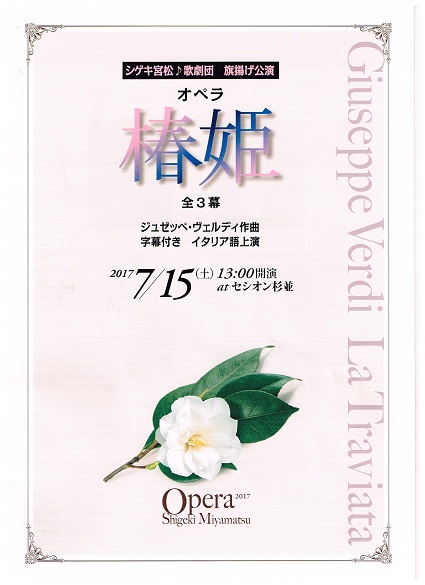
オーケストラ
:
シゲキ宮松♪歌劇団オーケストラ
合唱
:
シゲキ宮松♪歌劇団コーラス
合唱指導
:
森口 賢二
演出・美術
:
馬場 紀雄
照明
:
(株)ASG
衣裳
:
(株)エフ・シー・ジー
舞台監督
:
(有)加藤事務所
ヴィオレッタ
:高橋 薫子
アルフレード
:笛田 博昭
ジェルモン
:森口 賢二
アンニーナ
:但馬 由香
フローラ
:濱田 紫織
ガストン子爵
:澤崎 一了
ドビニー侯爵
:柿沼 伸美
ドゥフォール男爵
:若尾 隆太
グランヴィル医師
:鈴川 慶二郎
ジュゼッペ
:小美濃 奎允
使者・召使
:品田 広希
ダンサー
:山下 弘樹
感 想
ベテランの魅力・中堅の力-
シゲキ宮松♪歌劇団旗揚げ公演「椿姫」を聴く高橋薫子といえば、ソプラノ・リリコ・レジェーロの日本を代表する歌手の一人で、「愛の妙薬」のアディーナや「セビリアの理髪師」のロジーナ、「コジ・ファン・トゥッテ」のデスピーナなどでその魅力を示してきたわけですが、ヴェルディやプッチーニの重い役はあまり歌ってきておりませんし、また歌ったときは彼女にしてはあまり良い出来ではないことが多かったと思います。今回のヴィオレッタについてはかつて演奏会形式で歌った経験はありますが、舞台初役ではないでしょうか? それだけに正直申し上げればヴィオレッタもあまりうまくいかないのではないか、という予想をして伺いました。
ところが実際の歌、私の予想をはるかに超える素晴らしいヴィオレッタでした。正直に申し上げれば、声の張りという点では彼女より魅力的な方はたくさんいらっしゃると思います。例えば、「ああ、そは彼の人か~花から花へ」での高音のアクートみたいなところですね。だから、大向こうを唸らせるようなヴィオレッタではありません。しかし、表情がとても豊かで、ヴィオレッタの不安が歌にきっちり乗って出てくる。もちろん、それは第二幕のジェルモンとの二重唱など、ヴェルディがそう書いたところで顕著なのですが、例えば第一幕の「乾杯の歌」のあとのアルフレードとの二重唱みたいなところでしっかり示されてくる。要するに表情の出し方が繊細で丁寧なのです。
高橋は大学で教鞭をとるようになってずいぶん経ち、弟子の数も増えました。お弟子さんにはヴィオレッタを教えることもあるでしょう。そういう楽譜を読み込む中で彼女なりのヴィオレッタ像ができ、それを彼女のできる無理のないテクニックで示した、ということだろうと思います。これぞベテラン、とでも言うべき歌唱でした。。
この高橋の繊細な歌唱と比較すると。笛田博昭のアルフレードは一本調子です。もちろん声は凄い。今日本で一番乗っているテノールです。それだけのことはあります。声は艶やかでよく響きますし、アクートの決めなども流石というしかありません。すなわちテノールを聴くという観点から言えば最高なのですが、高橋と絡むと甘さが見えてしまう。例えばクレッシェンド・ディミニエンドなどが高橋であれば言葉のニュアンスに合わせて速度が変わってくるのですが、笛田はストレートで強くなり、ストレートで弱くなるみたいなところですね。
あと更に一つ申し上げるならば、笛田のアルフレード、ダメ男の表出がいまいちよろしくない。どこまでもかっこいいんです。声も立派ですし。しかし、あの立派な歌を聴いていると、アルフレードとしてはちと物足りなさを感じてしまったのもまた事実です。
森口賢二のジェルモン。歌はよかったです。流石に中堅実力者の歌でした。でもヴィジュアルがジェルモンとしての貫禄が感じられませんでした。もともと森口はスマートで身のこなしなどもスマートでフィガロのような活発な役をやれば生える方ですが、今回はそのもって生まれた身の動きが、ジェルモンの雰囲気をスポイルしたように思います。
その他の歌手ではアンニーナの但馬由香、ガストンの澤崎一了が見事な歌唱を示し、ベテラン柿沼伸美も存在感のある歌唱・演技でよかったです。それ以外の出演者は舞台経験が少ないのでしょう。まだまだこれからだな、という印象でした。
合唱は特に女声が市民合唱と雖も必ずしも鍛えられていないレベル。オーケストラは強奏やメロディラインの表情はしっかりしていましたが、弱奏になると今一つ腰が引けている印象でした。宮松重紀の指揮は取り立てて特徴的なものではないと思いました。
馬場紀雄の演出は限られた予算の中でしっかりメリハリをつけたオーソドックスなもの。「椿姫」はオーソドックスな演出が似合います。
いろいろ書きましたが、主要三役がみなそれぞれ立派で、脇役も但馬、澤崎、柿沼などがしっかり固め、見事なプロダクションだったと思います。その意味で一番残念だったのは会場かもしれません。このメンバーだったら、もっと席数の多いホール(セシオン杉並は578席でほぼ満席でした)でも十分お客さんを呼べると思いますし、もう少し響くホールであれば更に音楽的にも楽しめたように思います。
![]()
鑑賞日:2017年7月23日
入場料:自由席 4000円
主催:モーツァルトホールでオペラを上演する会(Le voci)
Le voci公演
全2幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演
ドニゼッティ作曲「愛の妙薬」(L'ELISIR D'AMORE)
台本:フェリーチェ・ロマーニ
会場 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
スタッフ
出 演
指揮
:
安藤 敬
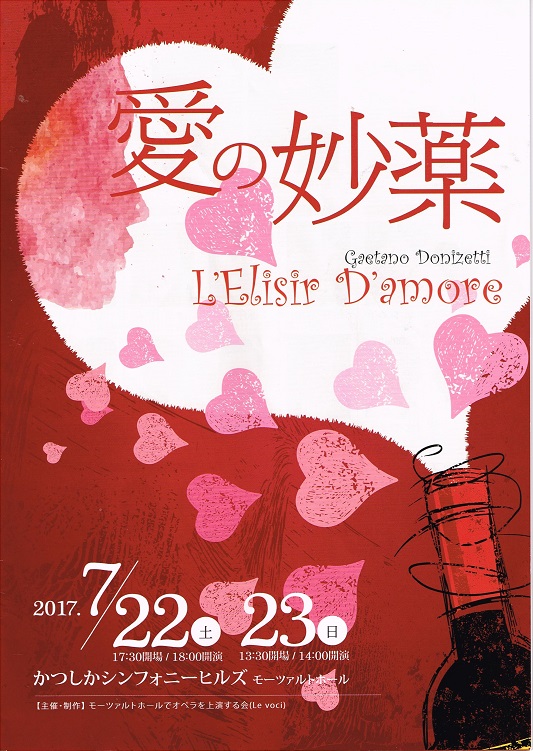
オーケストラ
:
テアトロ・フィガロ管弦楽団
合唱
:
テアトロ・フィガロ合唱団
演 出
:
奥村 啓吾
装置
:
鈴木 俊朗
照明
:
稲葉 直人
衣裳
:
森 眞佐乃
舞台監督
:
南 清隆
アディーナ
:中畑 有美子
ネモリーノ
:松尾 順二
ベルコーレ
:上田 誠司
ドゥルカマーラ
:三浦 克次
ジャンネッタ
:朝倉 春菜
感 想
トラブルシューティング-
Le voci「愛の妙薬」を聴く舞台上では、なんでもあり得ますし、現実にいろいろな問題が起きます。私もなんだかんだで、1000舞台以上実演を見ていると思いますが、いろいろなものを見せてもらいました。演奏中、ヴァイオリン奏者が高熱で倒れた演奏会や、指揮者が指揮棒を折って、その先端を手に刺してしまった演奏会の経験もあります。また、オペラでは、走って入ってくる歌手が舞台で「スッテーン」でこけたのも見たことがありますし、「魔笛」のパパゲーノが、自分の身体から「鳥」を飛ばすという演出で、鳥についている糸が絡まって飛べなかった、などというのもあります。出演している方に聴くと、小さなトラブルは「必ず」といってよいほど起きるそうで、何もない方が珍しいそうですが、一番厄介なのは出演者の声のトラブルです。
今回はアディーナ役は党静子がアナウンスされていたわけですが、突然の声のトラブル。開演して党が登場しましたが、その登場のアリア「無情なイゾルデに」でほとんど声が出ません。どうするのだろう、と思っていたら、すぐさま昨日の主役・中畑有美子がオケピットに入って歌い始めました。すなわち演技は党、歌唱は中畑、という「口パク」状態になりました。これは正直申し上げてうまいやり方ではありません。演技をしている方と全然違った方から声が聴こえてくるわけですから、ものすごい違和感があります。
こういう場合の正しい対処法は、開演時に党に因果を含めて降りてもらう。それがベストです。しかし、党は「歌える」と主張したのでしょうね。そこで鬼になり切れなかった主催者の責任は重いのですが、仮に歌わせると決めても、中畑に衣裳まで着てスタンバイしてもらい、最初のシーンが終了してアディーナが戻ってきたところで、交代させるのがセカンドベストだと思います。
口パクは歌っている方と演技している方が違うわけですから、合わせようとすればお互いに譲り合うしかありません。結果として第一幕のアディーナは終始ピントがぼけており、すっきりしないで終わりました。考えうるやり方の中で、一番悪いやり方を選択したな、というのがわたくしの感想です。
もちろん党は二幕は降板し、中畑が代役を務めました。この中畑が非常に素晴らしい歌唱。第一幕とは全然違いました。一幕のフラストレーションを晴らすような歌と申し上げてよいのでしょう。自分の演技のタイミングで歌えるということが、彼女にも歌いやすさを与えたと思いますし、代理で歌うことで、党静子の分もしっかり歌いたいという気持ちもあったのでしょう。違う組の方が相手で、一度も合わせはやっていないと思いますが、溌溂とした伸びやかな歌唱で、聴き手を唸らせました。大変立派だったと思います。
主役の「声のトラブル」ということでどうしてもそこに話題が行きがちですが、それ以外にも残念なところはあり、プロダクションとして十分満足できた、とまでは言えませんでした。まず何といってもネモリーノがブレーキ。この松尾というテノール全然歌えない。上が重く、高音は全てと申し上げてよいほど下がっていました。登場のアリアで仰天し、その後も突っ込みどころ満載の歌。途中は所々いいところもあったのですが、一番の聴かせどころである「人知れぬ涙」も全然魅力的ではありませんでした。先日、わたくしの友人(正式な音楽教育を受けていない完全なアマチュアです)が「人知れぬ涙」を歌ったのですが、失礼ながら、その友人よりも低レベルだったと思います。
上田誠司のベルコーレは、歌はそれほど悪いと思わなかったのですが、何を言っても演技にメリハリがない。ベルコーレはこのオペラ随一のボケ役です。そのボケの部分を大げさに強調しないとベルコーレのキャラクターが立ってこないのですが、そこが今一つピンボケです。演出の問題なのでしょうが、もう少しコメディーを強調すべきだったと思います。
一方、三浦克次のドゥルカマーラ、日本を代表するドゥルカマーラ歌いだけあって貫禄が違います。自分に観客の目を引き込ませるためにはどうしたらよいかをよく知っているようです。結果として、非常に魅力的なドゥルカマーラになっていました。登場のアリアである「お聞きなさい、村の衆」や、アディーナとの二重唱がよいのは当然ですが、それ以外の細かい処でも、見事な技量を示したと思います。
安藤敬の指揮は丁寧で適度に熱がこもってもあり、推進力もあって、まあまあ良かったと思います。オーケストラもミスは散見されましたが、全体としては十分なもの。奥村啓吾の演出もベルコーレの見せ方など疑問もありましたが、全体としてはオーソドックスでよかったと思います。
そして、もう一つ褒めるべきは合唱。市民オペラレベルの合唱とは一線を画するレベルと申しあげられると思います。パワフルだし、音声もきれいだし。これで男声がもう少し補充されれば厚みといい広がりといい文句なしと申し上げられると思います。
以上、持っているレベルは高いグループであることは分かりましたが、それを表出の仕方としては今一つ物足りなさも残り、主役の降板も相まって、成功とはいえないのかなというのが本当でしょう。
![]()
鑑賞日:2017年7月23日
入場料:自由席 6000円
主催:南條年章オペラ研究室
南條年章オペラ研究室~ピアノ伴奏演奏会形式によるオペラ全曲シリーズ Vol.17
ヴィンチェンツォ・ベッリーニ全オペラ連続演奏企画 第7回
全2幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演/演奏会形式
ベッリーニ作曲「カプレーティ家とモンテッキ家」(I Capuleti e i Montecchi)
台本:フェリーチェ・ロマーニ
会場 王子ホール
スタッフ
出 演
指揮
:
佐藤 宏
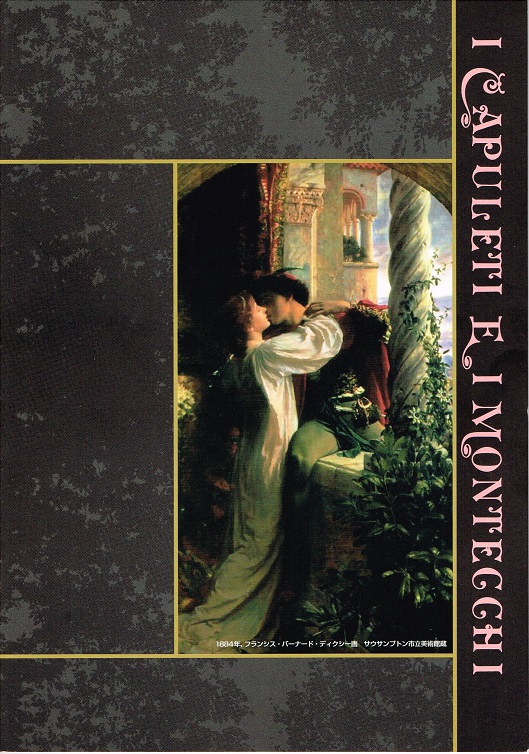
ピアノ
:
村上 尊志
合唱
:
南條年章オペラ研究室メンバー
ジュリエッタ
:平井 香織
ロメオ
:鳥木 弥生
テバルド
:青柳 明
カペッリオ
:小林 秀史
ロレンツォ
:坂本 伸司
感 想
テクニックと情感と-
南條年章オペラ研究室「カプレーティ家とモンテッキ家」を聴く
Le
voci「愛の妙薬」終演後カーテンコールもそこそこにすぐに駆け付けたのですが、聴けたのは第4曲、ジュリエッタのカヴァティーナ「ああ、幾たびか」から。でもこの一番有名なアリアから聴けたことは大変ありがたいことでした。平井香織が抜群に上手です。平井が技術的に優れた歌手であることは申し上げるまでもないのですが、表現力も含めこの方の良さが滲み出るような歌でした。
「カプレーティ家とモンテッキ家」TOPに戻る
平井はオペラ出演の多い方ですが、いわゆる主演級というよりはアンサンブルで支えるみたいな立場で歌われることが多い。こういう役柄は大向こうを唸らせるような華やかさは必ずしもは必要ないのですが、正確な音程、正確なリズムで合わせられなければいけません。平井はそういう技術が高く、新国立劇場のアンサンブルに平井が入ると舞台が締まる、というのはかつて何回か経験したところです。
今回の歌はよく考えられた歌で、息が長くてしっとりとした情感もあって、ロマンティックな味わいのある見事な歌でした。華やかさもあり、表情が豊かでフォルテッシモからピアニッシモまで安定した発声でまさに学生のお手本になるような歌。ほんとうに感心しました。
相手のロメオ役の鳥木弥生は声のパワーは平井よりも上ですし、持ち声も良い。ドラマティックな表現力も流石と申し上げるべきでしょう。ただ、平井と比較すると、自分の才能に任せて歌っている感じがするところがあります。もちろん、そういうことができるのは物凄いアドヴァンテージですが、ここで平井ほどの戦略を持ってクレバーに歌われたらどれだけ凄いのだろうと思ってしまうのです。
でもこのコンビだと、二重唱は絶妙というしかありません。知性の平井と才能の鳥木ががっぷり四つに組むとそれは見事なものでした。
男声陣はこの二人と比較すると一段弱いのは仕方がないでしょう。それでも小林秀史・カペッリオは立派でした。坂本伸司のロレンツォも悪くないのですが、この方声のコントロールが上手く行っていなくて、フォルテが強すぎるところがままあります。役柄的にはもう少し引いたほうがよいと思いました。
佐藤亜希子、小林厚子といったソロ歌手級が何人も入った入った合唱団はもちろん素晴らしく見事でした。
「カプレーティとモンテッキ」は、昨年このグループが上演した「ザイーラ」からの転用が多い訳ですが、昨年ザイーラを聴いた時はなんか音楽がよそよそし気に聴こえたのですが、「カプ・モン」は何度も聞いているせいか、親しみを感じました。似たような曲なのに、その違いが出たことが不思議です。なお、今回の公演、皆さん上手だとは思いましたし、レベルの高い演奏会だったのですが、何となく物足りなさもあります。昨年秋、藤原歌劇団はこの作品を上演しましたが、そのときの気持ちの盛り上がりと比較すると凄く冷静に聴いてしまった感じがするのです。演奏会形式は音楽の骨格が露わになってしまうので、複雑な音符構成のオペラはそれを面白く聴けるのですが、ベッリーニのように伴奏が比較的単純なオペラは、骨格が露わになりすぎて、オペラを楽しむ、という感じにはならないのかな、と思ってしまいました。
本ページTOPに戻る![]()
主催:公益財団法人びわ湖ホール/公益財団法人愛知文化振興事業団/公益財団法人東京都歴史文化財団/公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団/公益財団法人東京二期会/公益財団法人読売日本交響楽団/公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団
グライドボーン音楽祭との提携公演(東京二期会オペラ劇場公演)
全3幕、字幕付原語(ドイツ語)上演
リヒャルト・シュトラウス作曲「ばらの騎士」(Der
Rosenkavalier)
台本:フーゴ・フォン・ホーフマンスタロール
会場:東京文化会館大ホール
スタッフ
| 指揮 | : | セヴァスティアン・ヴァイクレ |
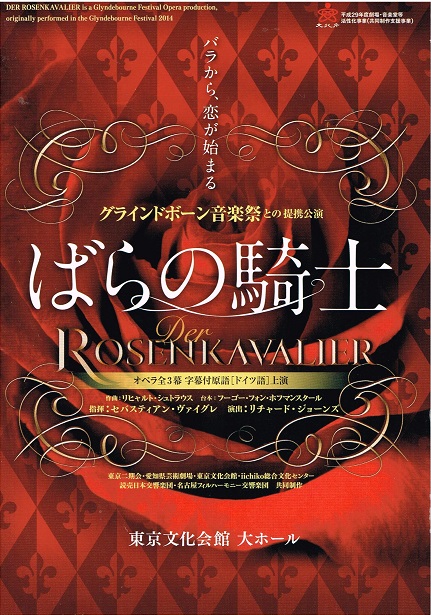 |
| オーケストラ | : | 読売日本交響楽団 | |
| 合唱 | : | 二期会合唱団 | |
| 合唱指導 | : | 大島 義彰 | |
| 児童合唱 | : | NHK東京児童合唱団 | |
| 児童合唱指導 | : | 金田 典子 | |
| 演出 | : | リチャード・ジョーンズ | |
| 装置 | : | ポール・スタインバーグ | |
| 照明 | : | ミミ・ジョーダン・シェリン | |
| 衣裳 | : | ニッキー・ギリブランド | |
| 演出補・振付 | : | サラ・フェイ | |
| 音楽アシスタント | : | 森内 剛 | |
| 舞台監督 | : | 幸泉 浩司 |
出 演
| 元帥夫人 | :林 正子 |
| オックス男爵 | :妻屋 秀和 |
| オクタヴィアン | :小林 由佳 |
| ゾフィー | :幸田 浩子 |
| ファーニナル | :加賀 清孝 |
| マリアンネ | :栄 千賀 |
| ヴァルツァッキ | :大野 光彦 |
| アンニーナ | :石井 藍 |
| 警部 | :斉木 健詞 |
| 元帥夫人家の執事 | :吉田 連 |
| ファーニナル家の執事 | :大川 信之 |
| 公証人 | :畠山 茂 |
| 料理屋の主人 | :竹内 公一 |
| テノール歌手 | :菅野 敦 |
| 三人の孤児 | :大網 かおり/松本 真代/和田 朝妃 |
| 帽子屋 | :藤井 玲南 |
| 動物売り | :芹澤 佳通 |
感 想
神は細部に宿る-東京二期会オペラ劇場公演「ばらの騎士」を聴く
前回二期会が「ばらの騎士」を取り上げたのが2003年のこと。二期会創立50周年記念公演の最後を飾るものだったと覚えております。その時の舞台はギュンター・クレーマーのケルン市立歌劇場のものを借りてきてきたわけですが、印象はすごい即物的で、音楽も即物的で全然納得のいくものではありませんでした。それから14年、東京二期会また新たな舞台を借りてきて上演いたしました。それが見事に前回のもやもや感を払拭するような舞台であったら喜ばしかったのですが、残念ながら、中途半端ないまいちの舞台を作ったな、というところです。
まず、ヴァイクレ/読売日響の音楽づくりが私の趣味とは違います。レガートに滑らかに流れるという印象がない。まず冒頭のファンファーレからオーケストラの中の受け渡しが微妙にうまくいっていない感じで、官能美が全く感じられない。最初の元帥夫人とオクタヴィアンの二重唱。この部分はオーケストラが色っぽく伴奏して、後朝の別れを演出すべきところですが、オーケストラが全然色っぽくない。特に今回の演出、元帥夫人がシャワーを浴びていて、それをオクタヴィアンが見ながら歌うという演出だったわけですが、ベッドを使う普通の演出と比較すると即物的です。こういう演出に付けるからこそ、もっともっと音が官能的にならないといけないと思うのですが、ヴァイクレはそういう風に振らなかった、ということだろうと思います。
ヴァイクレの今回の指揮は基本的に鈍重であり、場面場面での切り替えもあまり明確ではありませんでした。「オックス男爵のワルツ」のようにオーケストラがよく演奏する部分はオーケストラが指揮者を引っ張っている感じもしました。ここはもっと軽く演奏すればよいのになあ、とか、この部分はもっとレガートに演奏させればよいのになあ、と思う部分ばかりで、聴いていてイライラするほどでした。ちなみに休憩時間にロビーではクラシカ・ジャパンが宣伝を行っており、1994年のカルロス・クライバー指揮の「ばらの騎士」を映写しておりましたが、あのウィーン・フィルの音、今回の読売日響の音とは全然違います。今の読響は20年以上前のウィーンフィルより技術が上だと思うのですが、そういう音にならないところに、今回の上演の悲しさがあるように思います。
そんな中で歌手陣は頑張っていたと思います。特によかったのはオクタヴィアン役の小林由佳とオックス役の妻屋秀和。
小林は高音部やや喉声になって不安定になる部分があったのですが、全体的にはオクタヴィアンの役を考えた見事な歌唱だったと思います。特に冒頭のモノローグやオックスとの掛け合い、ゾフィーとの二重唱などオクタヴィアンの魅力をふんだんに振りまく歌唱は、見た目のかっこよさも相俟って大変素敵でした。
妻屋秀和のオックスもよい。日本を代表するバス歌手だけのことはあるということでしょう。特に低音の響かせ方の見事なこと。さすがと申し上げるしかありません。また、演技も上手で、田舎貴族の傍若無人さの出し方など流石で、この態度ならゾフィーに嫌われるだろう、と納得いくものでした。
「ばらの騎士」というオペラは「フィガロの結婚」のパロディですが、貴族社会への批判というよりは、貴族社会の没落へのオマージュとなっているように思われてきました。貴族社会にだけ許される退廃した恋愛関係が前提としてあり、元帥夫人とオクタヴィアンの恋愛がその典型です。元帥夫人は「老い」を感じており、自分よりずっと若いオクタヴィアンはいつか自分から離れていくだろうと思っている。貴族社会の没落と元帥夫人の老いが同調しているとも考えられ、そのような演出が多かった。
しかし、今回のジョーンズの演出はロマンティックなセンチメンタリズムを排しているところにその特徴があります。性愛を直接描いているわけではもちろんないのですが、恋愛の形而上的な感覚よりもいろいろなところで即物的に描こうとします。舞台の色使いも華やかですし、ポップなイメージが強い。演出家は例えば、元帥夫人はオクタヴィアンをゾフィーに渡した後、新たに若い燕を作るに違いないと考えているわけです。それが元帥夫人の第3幕の華やかな衣装にも出ています。
結果として林正子のマルシャリン。そういう演出に殺された感じがします。例えば、第一幕最後のモノローグ。もちろんしっかり歌われているのですが、どこか今一つ自分自身で納得できていないようなよそよそしさを感じてしまいました。また第三幕の三重唱も素敵ではあるのですが、ちょっと存在感が薄い感じ。リヒャルト・シュトラウスの音楽に一番寄り添う役柄が元帥夫人だと思うのですが、演出でそこが規制されたため、乗り切れなかったのでしょうか。
ほとんどが前回(2003年)の公演と入れ替わった今回の上演でしたが、幸田浩子のゾフィーと加賀清孝のファーニナルが再演。どちらもあまり良いとは思いませんでした。幸田はもともと実力のある方ですから、しっかりまとめてくるんですけれども、ゾフィーの若さを表現しきれていませんでした。ゾフィーは貴族社会にあこがれる軽薄な娘です。そのキャピキャピ感をどう表現するかだと思うのですが、歌に落ち着きがありすぎて違和感がありました。加賀清孝のファーニナルもあまりぱっとしませんでした。
それ以外の脇役陣は全体的にバランスが悪い感じがしました。細部にこだわって細かくきっちり構築していけばよいと思うのですが、主要役以外の方は力量的にも声質的にもバラバラで、まとまってこない印象が強いです。例えばテノール歌手。ストーリーには全く関係ない端役ですが、彼がしっかりと歌うと、あのたくさんの人が訪ねている時間が彼の声で整理されてまとまってくるのですが、今回のような歌だと、バラバラ感がますます強まります。そういうところをどこまで綿密に考えたのかな、というのが疑問です。
以上主要歌手は頑張っていて聴きごたえはあったのですが、オーケストラの音の作り方と脇役の細部の歌唱が物足りなく、全体としては残念な公演だったと言うべきでしょう。
![]()
![]()
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
