�I�y���ɍs���ĎQ��܂���-�Q�O�P�O�N�i���̂P�j
�ڎ�
| �^�����ȃK���R���T�[�g�@ | 2010�N01��06���@ | �V��������u�j���[�C���[�I�y���p���X�E�K���v���@ | |
| �I�y���̊y���܂����@ | 2010�N01��13���@ | �V��������n�揵�ٌ����@�D�y�����̌���u���𓐂b�v���@ | |
| B���I�y���̖��́@ | 2010�N01��17���@ | �����I�y���v���f���[�X�u�}�_���@�T���E�W�F�[�k�v���@ | |
| �M�C�����͕����Ă��Ȃ��@ | 2010�N01��31���@ | ����s���I�y���u�A�C�[�_�v���@ | |
| ���j�E������m��Ƃ��������@ | 2010�N02��07�� | �����̌��c�u�J��������C�����̑Θb�v���@ | |
| ����I�e���͕���Ȃ��@ | 2010�N02��17���@ | ���������I�y������u�I�e���v���@ | |
| ���[�c�@���g�̎Ꮡ���@ | 2010�N02��18���@ | ���������̌���u�U��̏���t�v���@ | |
| ���H�l��̃I�y���@ | 2010�N02��23���@ | �V��������u�W�[�N�t���[�g�v�� | �@ |
| ���ڂQ���[�g���@ | 2010�N03��05���@ | �������y��w�~�T���g���[�z�[���I�y���E�A�J�f�~�[�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���@ | �@ |
|
�V�l�������V�l |
2010�N03��11���@ | �V��������I�y�����C�����C�����u�t�@���X�^�b�t�v���@ | �@ |
�ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2009�N��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2009�N���̂S��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2009�N���̂R��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2009�N���̂Q��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2009�N���̂P��
�ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2008�N��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2008�N���̂S��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2008�N���̂R��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2008�N���̂Q��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2008�N���̂P��
�ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2007�N��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2007�N���̂R�w
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2007�N���̂Q�w
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2007�N���̂P��
�ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2006�N��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2006�N���̂R��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2006�N���̂Q��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2006�N���̂P��
�ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2005�N��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2005�N���̂R��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2005�N���̂Q��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2005�N���̂P��
�ǂ����[�s�̃I�y���x�X�g�R�@2004�N��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2004�N���̂R��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2004�N���̂Q��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2004�N���̂P��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2003�N���̂R��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2003�N���̂Q��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2003�N���̂P��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2002�N���̂R��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2002�N���̂Q��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2002�N���̂P��
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2001�N�㔼��
�I�y���֍s���ĎQ��܂���2001�N�O����
�I�y���ɍs���ĎQ��܂���2000�N���@

![]()
�ό����F2010�N1��6��
���ꗿ�FZ���@1500�~�@4FL8��1�ԁ@
��ÁF�V��������
�V��������I�y���E�o���G
�u�j���[�C���[�I�y���p���X�K����iNEW NATIONAL THEATRE,
TOKYO OPERA&BALLET, NEW YEAR OPERA PALACE
GALA)
���F�@�V��������I�y������
�v���O����
��ꕔ�F�o���G
�w���@
�@
���@���j�@
�nj��y�@
�@
�����t�B���n�[���j�[�����y�c�@
�Ɩ��@
�@
����@��O�@
����ē@
�@
�X���@���@
�@
�@
�@
�u�O�����E�p�E�h�E�t�B�A���Z�v�i�V����j�@�@�@
�U�t�@
�@
�W���b�N�E�J�[�^�[�@
�X�e�[�W���O�@
�@
�q�@�������@
���y�@
�@
�`���C�R�t�X�L�[�@
�o���@
�@
�����Ƃ������@
�@
�@
�{���@���a�@
�@
�@
����@���q�@
�@
�@
���c�@�����@
�@
�@
�����@�����q�@
�@
�@
�ɓ��@�^���@
�@
�@
�@
�u�W�v�V�[�j�݁v������s�i���@�@�@
���y
�@
���n���E�V���g���E�X�U���@
�@
�@
�@
���[�����E�v�e�B�́u��������v���u�O�����E�J�t�F�v�@�@�@
�U�t�@
�@
���[�����E�v�e�B�@
���y�@
�@
���n���E�V���g���E�X�U���@
������p�@
�@
�W�������~�V�F���E�E�B�����b�g�@
�ߏց@
�@
���C�U�E�X�s�i�e�b���@
�Ɩ��@
�@
�}���I���E�E�[���b�g�^�p�g���X�E���V�����@���G�@
�o���@
�@
����@�����q�i�x���j�@
�@
�@
�팩�@�q�F�i���n���j�@
�@
�@
�g�{�@�v�i�E�����b�N�j�@
�@
�@
�V��������o���G�c�@
��F�I�y��
�X�^�b�t
��ȉƁ@ �I�y����i���@ �A���A���@ �o���ҁ@ �����ҁ@
�w�@���@
:�@
�e�r�@�F�T�@
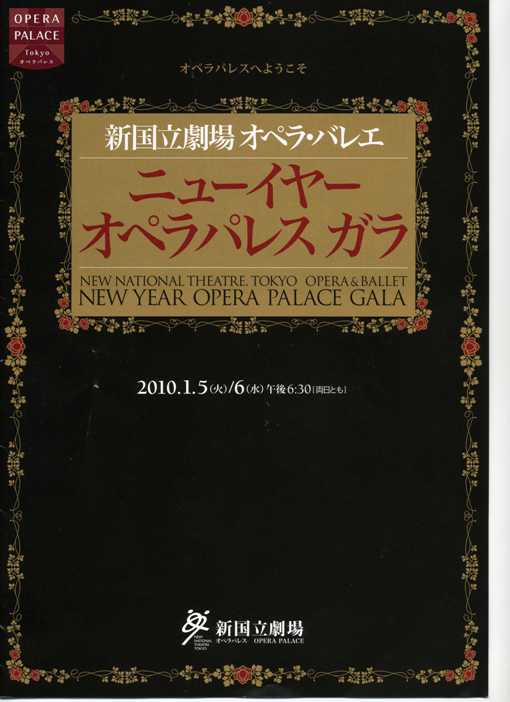 �@
�@
�nj��y�@
:�@
�����t�B���n�[���j�[�����y�c�@
���@���@
:�@
�V�������ꍇ���c�@
�����w���@
:�@
�O�V�@�m�j�@
���@�o�@
:�@
�O�Y�@���_�@
������p�@
:�@
���c�@���q�@
�Ɓ@���@
:�@
����@��O�@
���@���@
:�@
���c�@�b�q�@
����ē@
:�@
��m�c�@��F�@
�v���O����
���F���f�B�@
�A�C�[�_
�����A�C�[�_�@�@
�]�����E�g�h�����B�b�`�i�e�m�[���j�@
�@
�@
�@
�����ċA��@
�m���}�E�t�@���e�B�[�j�i�\�v���m�j�@
�@
�@
���S���b�g�@
��킵���l�̖��́@
�K�c�@�_�q�i�\�v���m�j�@
�V�������ꍇ���c
�i�\���F�n�ӕ��q�i�e�m�[���j�A�쑺�͐m�i�o���g���j�A���i��Y�i�o���g���j�@
�@
�֕P�@
�v�����@���X�̊C�Ɨ��@
�x���@�N�Y�i�o���g���j�@
�@
�I�b�t�F���o�b�N�@
�z�t�}������@
�́A�A�C�[�i�b�n�̋{��Ɂ@
�]�����E�g�h�����B�b�`�i�e�m�[���j�@
�V�������ꍇ���c�i�\���F�n�ӕ��q�i�e�m�[���j�j�@
�@
�@
���_�ɏ����������@
�K�c�@�_�q�i�\�v���m�j�@
�V�������ꍇ���c�@
�W�����_�[�m�@
�A���h���A�E�V�F�j�G�@
�c���̓G�@
�x���@�N�Y�i�o���g���j�@
�@
�v�b�`�[�j�@
�}�m���E���X�R�[�@
�ЂƂ�₵���A�̂Ă��ā@
�m���}�E�t�@���e�B�[�j�i�\�v���m�j�@
�@
�}�X�J�[�j�@
�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�@
���t�̉́@
�]�����E�g�h�����B�b�`�i�e�m�[���j�@
�V�������ꍇ���c�i�\���F���Y��i���]�\�v���m�j�j�@�@
�A���R�[���@�@�@�@�@
�v�b�`�[�j�@
�g�X�J�@
�̂ɐ����A���ɐ����@
�m���}�E�t�@���e�B�[�j�i�\�v���m�j�@
�@
���F���f�B�@
�֕P�@
���t�̉́@
�]�����E�g�h�����B�b�`/�K�c�_�q�@
�V�������ꍇ���c
���@�z�@�^�����ȃK���E�R���T�[�g�|�V��������u�j���[�C���[�I�y���p���X�E�K���v��
�@�V�N���j���K���R���T�[�g�́A�e�I�[�P�X�g���𒆐S�ɍs���Ă���悤�ł����A�I�y���̐��E�ł�NHK�̃j���[�C���[�I�y���R���T�[�g�����߁A����������悤�ł��B�V��������ł���N����u�j���[�C���[�E�I�y���p���X�K���v�Ə̂����K���R���T�[�g���n�߂܂����B���́A��N�͍s���Ȃ������̂ł����A���N�̓e���r�Ō���NHK�̃j���[�C���[�I�y���R���T�[�g�����܂�ɂ��C�ɓ���Ȃ������̂ŁA�������ɂȂ�Ȃ����ƓˑR�v�������A�������œ��ꂵ�܂����B���߂Ă�Z���ł��B
�@�ꌾ�Ő\���グ��A�܂��܂��̃R���T�[�g�������Ɛ\���グ��̂��K���낤�Ǝv���܂��B�����ĉ₩�ȃK���E�R���T�[�g�炵���K���E�R���T�[�g�ł͂Ȃ������Ǝv���̂ł����A����̃e���r�Ō���NHK�̃j���[�C���[�I�y���R���T�[�g���͂����Ƃ܂��ȏo���ŁA�ق��Ƃ������܂����B
�@���̓o���G�ɂ��Ă͂قƂ�nj������Ƃ�����܂��A�[���m�����Ȃ��̂ŁA��ۈȊO�����\���グ�邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�݂Ȃ������ɏ��ɗx��ȁA�Ǝv���܂����B�Z�I�I�ɂ́u�O�����E�p�E�h�E�t�B�A���Z�v�̂ق�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂������A�������̉₩�ȋC���ɂ��}�b�`�����̂͌㔼�̃��[�����E�v�e�B�́u��������v�ł��B����̎O�l�̗x������邱�ƂȂ���A�O�l�̃M�����\���̗x���A3�l�̃O���[�b�g�̗x����y���߂܂����B�����A���͍��{�I�Ɂu�̍D���v�Ȃ̂ł��傤�ˁB�o�����[�i�����̗x�肪��肾�Ǝv���Ȃ�����A�̂̂Ȃ��u��������v�͂���ς�Ԕ������ȁA�Ǝv���Ă���܂����B
�@�㔼�̃I�y���ł����A4�l�̉̎肪����2�Ȃ��̂��\���B����͐V��������ł͔��ɏo���̑����A�l�C�̃\�v���m�A�m���}�E�t�@���e�B�[�j�ƁA��͂艽�x���o�ꂵ�Ă���e�m�[���A�]�����E�g�h�����B�b�`�A���{������͍K�c�_�q�i�\�v���m�j�Ɩx���N�Y�i�o���g���j���o�ꂵ�܂����B
�@�̏��͑S�ʂɗǍD�Ɛ\���グ�Ă悢�̂ł��傤�B
�@�ŏ��̃g�h�����B�b�`�́u�����A�C�[�_�v�́A�ނ̖{���̐��ɂ͍����Ă��Ȃ����̂ł����B���́A���̋Ȃ͍������ӂ���Ƌ�������悤�ȉ̂������D���Ȃ̂ł����A�g�h�����B�b�`�́A�����グ��悤�ȉ̂������������܂����B�͋����̂ł����A���̋Ȃ̎��R����������Ȃ��̂ŁA���܂芴�S�ł��܂���ł����B�������A����ȊO�͊F���i�_�̉̂ł����B
�@�t�@���e�B�[�j�́u�����ċA��v�́A�������Ɂu�A�C�[�_�v�Ӗ��Ƃ��Ă������������܂��B�A�C�[�_�̔��݂̋C������ǂ��\���������͓I�Ȃ��̂������Ǝv���܂��B�K�c�_�q�́u��킵���l�̖��́v�͑�ł͗ǂ��܂Ƃ߂Ă����Ǝv���܂����A�ׂ����Ƃ���̃R���g���[���������������ۂł��B���Ƃ��A�f�B�~�j�G���h���ď����������Ă����悤�ȕ����̉̏��ŁA�f�B�~�j�G���h�̃X�s�[�h����⑬��������Ƃ������Ƃ���ł��B�����A����ł�1��3���̃R���X�^���c�F���̂�������萺�ɐL�т₩��������܂����B3���͒��q�������A�{�����r��ɂ���Ƃ�����ۂ������܂����B�x���N�Y�́u�v�����@���X�̊C�Ɨ��v�͂������̉̏��������Ǝv���܂��B
�@�u�z�t�}������v�Ɉڂ��āA�܂��g�h�����B�b�`�́u�́A�A�C�[�i�b�n�̋{��Ɂv�́A�u�����A�C�[�_�v���͂����Ƒf�G�ȉ́B�����g�h�����B�b�`�̐����A���������̂Ɏ������Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�ˁB�V�������ꍇ���c���ǍD�ł����B�K�c�_�q�̃I�����s�A�̃A���A�́A�������K�c�_�q�Ɛ\���グ��ׂ������B���͕K��������D���ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A�K�c�ɂƂ��āu�I�����s�A�v�͂Ƃ��Ƃ�̂������̂悤�ŁA�ԑR�Ƃ���Ƃ��낪�Ȃ��̏��ł����B����Ȃ��ɂa���������ł��B
�@�x���N�Y�́u�c���̓G�v�����̉̏��ł��B�ǂ�����Ɨ��������������́A�W�F���[���̗h�ꓮ���C������\������ɏ\���̂��̂������Ɛ\���グ�ėǂ��Ǝv���܂��B�����āA�t�@���e�B�[�j�́u�ЂƂ�₵���A�̂Ă��āv�̓t�@���e�B�[�j�̗͂������̏��ł��邱�Ƃ͋^������܂���B���̃R���T�[�g�̃N���C�}�b�N�X�ɂӂ��킵���̏��������Ǝv���܂��B�Ō�́A�u�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�́u���t�̉́v�@����A���R�[����2�Ȃł����B�ŏ��ɉ̂�ꂽ�A�t�@���e�B�[�j�́u�̂ɐ����A���ɐ����v�͖{���̔����B�����̖����������Ǝv���܂��B�u�֕P�v�́u���t�̉́v�́A�J���@�����A�E���X�e�B�J�[�i�v�́u���t�̉́v�@��肸���Ɖ₩�ȕ��͋C������܂��B���̃K���E�R���T�[�g��߂�ȂƂ��Ă͏\���Ɛ\���グ����Ǝv���܂��B
�@�e�r�F�T�Ɠ����t�B���̉��t�́A�����������t��ǂ��������̂��ǂ��������Ă���������Ȃ̂ŁA���S���Ē����܂����B�@����͂��Ԃ�������������ȂǁA���₩�������o���Ă��ǂ��̂��ȁA�Ƃ��v���܂������A�V���v���ŗǂ��Ƃ��v���܂����B
�u�j���[�C���[�I�y���p���X�K���vTOP�ɖ߂�
�{�y�[�W�ŏ��ɖ߂�![]()
�ό����F2010�N1��13��
���ꗿ�F�w����@5670�~�@C1��14�ԁ@
��ÁF�����c�������@�l�@�D�y�����̌���/�V��������
����21�N�x�V��������n�揵�ٌ���
�D�y�����̌���
�I�y��2���@���{�����
�I���t��ȁu���𓐂b�v�iDer
Mond)
����F�O�������b�u���v�A��{�F�J�[���E�I���t
���{��A�ҋȁF��͒q�q
���F�@�V�������ꏬ����
�X�^�b�t
�|�p�ē@
�F�@
��́@�q�q�@
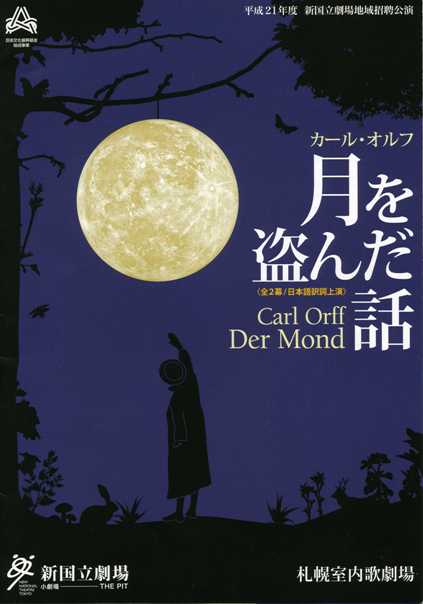 �@
�@
�w�@���@
�F�@
���V�@���j�@
���@�o�@
�F�@
���Á@�M�m�@
���@�p�@
�F�@
�O��@�i�q�@
�Ɓ@���@
�F�@
�����@�N�v�@
�w�A���C�N�@
�F�@
�����@����@
����ē@
�F�@
���@���s�@
���w���@
�F�@
�����@�q�q�@
�����y
| �t���[�g�^�s�b�R���@ | �F�@ | �y��@�H�q�@ |
| ���@�C�I�����@ | �F�@ | �x���@����@ |
| �`�F���@ | �F�@ | ���@���q�@ |
| �s�A�m�@ | �F�@ | �g���@���؎q�@ |
| �L�[�{�[�h�@ | �F�@ | ���@�u���@ |
| ����@ | �F�@ | �����@�̂�q�@ |
| �y�g���X�@ | �F�@ | �����@���l�@ |
| 4�l�̑��l�@ | �F�@ | �Γc�@�܂�q/�n�Ӂ@����/�E�c�@���q/���c�@�v���@ |
| �悻�̑��̑����@ | �F�@ | �Γ�@�����j�@ |
| �悻�̑��̔_���@ | �F�@ | ���{�@��O�@ |
| �悻�̑��̑��l�@ | �F�@ | ���c�@�N��/�V�Á@�k��/���@�T��Y/���@���m�@ |
| �����̑��̑��l�@ | �F�@ | �q�{�@�^��/�y�{�@����/��@����/���c�@���q/�����@��/�O�Y�@�u����/�X�@��G�q�@ |
| �������̏����@ | �F�@ | �V���@�x�q�@ |
| �q�������@ | �F | ����㏭�N���������c�@ |
�ό����F2010�N1��17��
���ꗿ�FB���@5000�~�@2F2��35�ԁ@
��ÁF�����I�y���E�v���f���[�X
�����I�y���E�v���f���[�X��85���������i35���N�L�O�����j
�I�y��3���@�����t������i�C�^���A��j�㉉�@���{����
�W�����_�[�m��ȁu�}�_���@�T���E�W�F�[�k�v�i�����Ă��鏗�j�iMadame
Sans-Gene)
����FV�E�T���h�D�[��E.�����[�A��{�F���i�[�g�E�V���[�j
���F�@�V�������ꒆ����
�X�^�b�t
�w�@���@
�F�@
���C�@�N���@
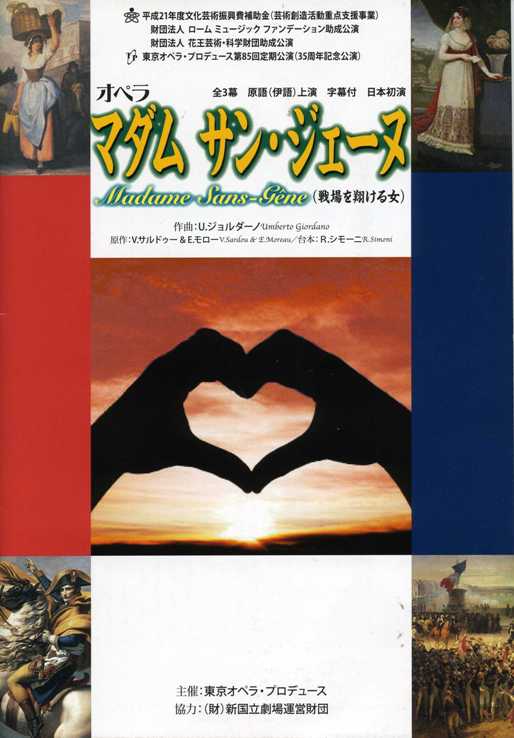 �@
�@
�I�[�P�X�g���@
�F�@
�����I�y���E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c�@
���@���@
�F�@
�����I�y���E�v���f���[�X�����c�@
�����w���@
�F�@
�ɍ����@�M��/�����@�����Y���q��@
���@�o�@
�F�@
���Ӂ@���j�@
���@�p�@
�F�@
�y���@�Ώ��@
�Ɓ@���@
�F�@
���c�@�r�Y�@
�w�A���C�N�@
�F�@
�c�@�O�@
����ē@
�F�@
����@���@
�X�[�p�[�o�C�U�[�@
�F�@
���@���s�@
�o��
| �J�e���[�i | �F | �e�n�@���� | |
| ���t�F�[�u�� | �F | �H�R�@�W�� | |
| �t�V�F | �F | ����@�q�s | |
| �i�|���I�� | �F | �H���@�_�� | |
| �i�C�y���O���� | �F | �n�@�p�K | |
| �g�j�I�b�^ | �F | �k�@�@��q | |
| �W���[���A/�r���[���[ | �F | �����@�Ďq | |
| ���@���b�T/�c�@ | �F | ���q���S�� | |
| �J�����[�i���� | �F | �]���@��� | |
| �G���[�U���� | �F | �㓡�@���� | |
| ���B�l�[�O�� | �F | �]���@���M | |
| �f�X�v���[ | �F | ���c�@���� | |
| �W�F���\�~�[�m | �F | ���ˁ@�~ | |
| ������ | �F | �}��@�m | |
| �u���S�[�h�D | �F | ����@�a�V | |
| ���X�^�� | �F | �����@�s�� | |
| �}�g�D���[�m�@ | �F�@ | �Ɠ��@�Î��n�@ |
�ό����F2010�N1��31��
���ꗿ�FB���@2000�~�@2F34��39�ԁ@
����s�s��70���N�L�O����
��ÁF����s���I�y���̉�/�i���j����s�n�敶���U�����c
����s���I�y��2010
�I�y��4���@�����t������i�C�^���A��j�㉉
���F���f�B��ȁu�A�C�[�_�v�iAida)
��{�F�A���g�j�I�E�M�X�����c�H�[�j
���F����s�s����فi�A�~���[��������j��z�[��
�X�^�b�t
�w�@���@
�F�@
�ÒJ�@����@
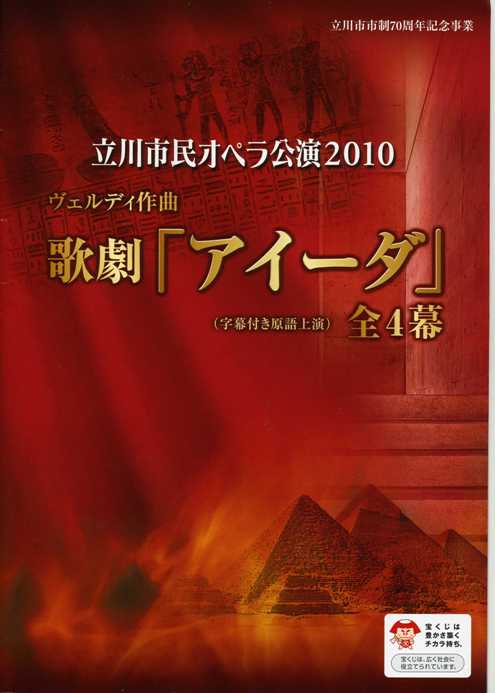
�I�[�P�X�g���@
�F�@
����nj��y�c�@
�o���_�@
�F�@
�������y��w�L�u
���@���@
�F�@
����s���I�y�������c�@
�����w���@
�F�@
�q���@�T�q/�{��@���q�@
�����@
�F�@
����s���I�y������2010���c�@
�o���G�@
�F�@
�W���p���E�C�i�^�[�i�V���i���E���[�X�E�o���G�@
���@�o�@
�F�@
�����@�h��@
���@�u�@
�F�@
���c�@���q�@
�Ɓ@���@
�F�@
�ΐ�@�I�q�@
�߁@�ց@
�F�@
���l�ā@��q�@
����ē@
�F�@
���V�@�T�@
�o��
| �A�C�[�_ | �F | �X�c�@��� |
| �A���l���X | �F | ���@���� |
| ���_���X | �F | ���@�a�h |
| �A���i�Y�� | �F | �q��@���l |
| �����t�B�X | �F | ��c���@��O |
| �G�W�v�g���� | �F | �F�J�@�K�G |
| �`�� | �F | ���ؑ]�@���� |
| �ޏ��̒� | �F | �V��@�ꗹ |
�ό����F2010�N2��7��
���ꗿ�FD���@5000�~�@4FL1��24�ԁ@
����21�N�x�����|�p�U����⏕���i�|�p�n���������ʐ��i���Ɓj
2010�s���|�p�t�F�X�e�B�o���Q������
��ÁF���c�@�l���{�I�y���U����/�Вc�@�l���{���t�A��
�����̌��c����
�I�y��3���@�����t������i�t�����X��j�㉉
�v�[�����N��ȁu�J��������C�����̑Θb�v�iDialogues des
carmélites)
��{�F�W�����W���E�y���i�m�X
���F����������ّ�z�[��
�X�^�b�t
�w�@���@
�F�@
�A�����E�M���K���@
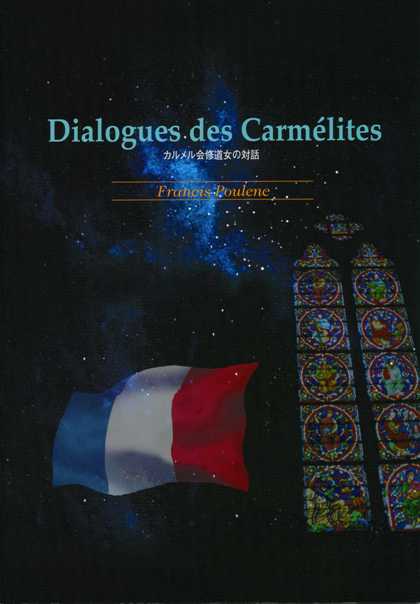
�I�[�P�X�g���@
�F�@
�����t�B���n�[���j�[�����y�c�@
���@���@
�F�@
�����̌��c�������@
�����w���@
�F�@
�ēc�@�^��@
���@�o�@
�F�@
���{�@�d�F�@
���@�p�@
�F�@
�r�c�@�ǁ@
�Ɓ@���@
�F�@
��c�@�S��@
�߁@�ց@
�F�@
�O���@���q�@
����ē@
�F�@
�����@�����O�@
�o��
�h�E���E�t�H���X���
�F
�O�Y�@����
�u�����V���E�h�E���E�t�H���X
�F
�����@����q
�R�m�t�H���X
�F
���R�@�z��Y
�N�����b�V�[�C���@��
�F
�S�@���q
���h���[�k�C���@��
�F
�{�{�@���q
�}�U�[�E�}���[
�F
�q��@�^�R��
�R���X�^���X�C����
�F
��с@�T�q
�}�U�[��W�����k
�F
��n�@���Îq
�}�e�B���h�C����
�F
���Y�@��
�i��
�F
���J�@����
��1�̐l���ψ�
�F
��v�ہ@���j
��2�̐l���ψ�
�F
�����@�Lj�
�W�������m(��t)
�F
�`���@�L��
�e�B�G���[(�]�l)/�Ŏ�
�F
��{�@�L�i
��l
�F
�H���@�_��
�}�U�[�E�W�F�U�[��
�F
�Ɠc�@�I�q
�N���[���C�����@
�F
�g���@�b
�A���g���[�k�C�����@
�F
����@������
�J�g���[�k�C�����@
�F
�����@���b
�t�F���V�e�B�C�����@
�F
�����@���a
�W�F���g�����[�h�C�����@
�F
���B�@������
�A���[�X�C�����@
�F
�{�{�@�ʉ�
���@�����e�B�[�k�C�����@
�F
�n�Ӂ@���[�U
�A���C�����@
�F
�g�c�@��b
�}���^�C�����@
�F
�R��@�m�q
�V���g���C�����@
�F
�A�n�@�R��
���@�z�@���j�E������m��Ƃ������Ɓ|�����̌��c�u�J��������C�����̑Θb�v��
�@�u�J��������C�����̑Θb�v�́A�t�����X�v�����̃R���s�G�[�j���̃J��������16�C�����̏}���i���Y�j���ނɂ����I�y���ł����A���������ƁA��X�́A�t�����X�̗��j��C����̃��[���b�p�ɂ�����ʒu�Â��A���̑��A���B�̂�����x���{�̂���l�����ɂƂ��Ă͏펯�̂��Ƃ��ǂ��������Ă��Ȃ��̂��ȁA�Ǝv���܂��B�u��X�v�A�Ə������̂́A��������v���O�����ɂ������i����ɂ��A��������������Ɋ�Â��L�q�����邩��ł��B�N�����V�[�C���@����h���[�k�C���@���́A����ǂ݂ŋL�ڂ���ƁA�}�_���E�h�E�N�����V�[�A�}�_���E���h���[�k�ɂȂ�̂ł����A�������{��ɂ��̂܂ܖāA�N�����V�[�v�l�A���h���[�k�v�l�Ə�����Ă���Ƃ��낪����܂��B�J�\���b�N�̏C�����͓Ɛg�������ł�����A���������v�l�ɂȂ�킯������܂���B�v����Ɂu�}�_���v�Ƃ����̂́A�_�ւ̋A�˂������ʊK�̈�ŁA�V�X�^�[�A�}�U�[�̏�̈ʂƂ������Ƃ̂悤�ł����A������������{�I�Ȃ��Ƃł���A��X�ɂƂ��ď펯�ł͂���܂���B
�@���̂悤�ȍ�i�w�i�ɑ��鍪���I�s���������邾���ɁA������₷�����o�͑厖���낤�Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŁA����̏��{�d�F�̉��o�́A�����Ԃ��ۓI�Ŏ��o�I�ɕ�����₷���悩�����Ǝv���܂��B�܂����̍�i�́A��ʂ̐ؑւ̑�����i�Ȃ̂ł����A�ؑւ̕����ł́A������̖����g���ĎՌ����A���̕���]��������Ԃ́A���̑O�ʼn��Z������Ƃ��������ŁA���y�̗�����ɗ͐�Ȃ��悤�ȍH�v������Ă��܂����B�܂��A�t�����X�v���̗���ɂ��Ă悭�m��Ȃ����O�̂��߂ɁA�x�e��̏��߂ɁA�t�����X�v���̎�v�Ȏ������X���C�h�ŔN�\�Ɏ����A�܂��A�Ō�̒f����̃V�[�����ɂ��Ă��A�f����͔w�i�����ɂ��炦�Ă���܂����A���̎���ɎE�C�Ɋւ���F�X�Ȏʐ^�𓊉e���āA���̏}���̖��Ӗ����𑊑ΓI�Ɏ������Ƃ��Ă��܂����B�Ō�̃X���C�h���e�́A���\���邳�����������܂������A�u�J��������v�Ƃ����I�y����i�𗝉����邽�߂ɂ͗ǂ���@�Ȃ̂�������܂���B
�@���Ȃ݂ɋx�e�͑���ꂠ�ƁA�C�������������h���[�k�V�C���@���̂��Ɓu�A���F�E�}���A�v���̂�����ł��B����͏C�����������f����ɏオ��Ƃ��ɉ̂���u�T�����F�E���W�[�i�v�ƌĉ�������Ӑ}���������̂ł��傤�ˁB���̋x�e�́A�O�㔼�̎��Ԃ��o�����X���Ă��āA�悢�Ǝv���܂����B
�@�w���̓A�����E�M���K�����A���t�͓����t�B���������܂����B���̃R���r�̉��t�́A�ᔻ������悤�ł����A��N�V��������I�y�����C�������グ���Ƃ��̓����j���[�V�e�B�nj��y�c�̉��t���͂邩�ɐ[�݂����������A�Z�܂��Ă����܂����B�v�[�����N�̔ӔN�̉��y�ɓ����I�ȈÂ�����߂��Ƒ��l�ȉ��y��@�����̍�i�̑傫�ȓ������Ǝv���̂ł����A�����͂�����x��������\���ł��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A��i�̂��Ƃ��Ƃ̐��i������̂ł��傤���A�㔼�̂ق������y�I�ٔ����͂������悤�Ɏv���܂��B
�@�̎�w�ō���ł����͓I�������̂́A�R���X�^���X���̂�����їT�q�B�R���X�^���X�́A�S�̓I�ɈÂ��g�[���ŕ`����邱�̍�i�̒��ŁA�B�ꖾ�邢�A�N�Z���g��^����ł����A���ɂ��Ă��\��ɂ��Ă��ޏ����̂��ƃp�b�ƋP�������������Ă悩�����ł��B
�@����̃u�����V�����̂�����������q�B�O���͍���p�b�Ƃ����A�㔼����Ԃ����Ƃ��������ł��B�����͈��N�̓잊�N�̓I�y���������Łu���N���c�B�A�E�{���W�A�v���A��ϊ��S�������Ȃ̂ŁA�傢�Ɋ��҂��čs�����̂ł����A����́A���̔�т�����ア��ۂł����B��ꂪ�L�����Ƃ��e�������̂ł��傤���B�܂��A�u�����V���Ƃ�������Ӗ��G�L�Z���g���b�N�Ȑ��i�̎�������̂����ɂ��ւ�炸�A�O���͉̏������ƂȂ����A�u�����V���ُ̈퐫�������яオ���Ă��Ȃ��Ƃ�����c�O�Ɏv���܂����B�㔼�͐���Ԃ��A�Ō�͂���Ȃ�ɒ��K�����킹�Ă����Ƃ͎v���܂��B
�@�x�e�����E�S���q�ɂ��N�����V�[�B�������ɐ��̗͂͐������B���܂���B����ł����Z��\��͔��^�̂��̂�����܂����B���̏�ʂ̏C�����ɂ���܂����l�ԏL���\������x�e�����̖��Ɛ\���グ��ׂ��Ȃ̂ł��傤�B
�@�������x�e�����E�{�{���q�ɂ�郊�h���[�k�B������͐��̗́A���Z�͋��ɍ���ł����B���h���[�k�́A�J����������Q���ꂽ��A�C���������̒��S�ɂȂ��Ă����Ȃ̂ŁA���[�_�[�Ƃ��Ă̑��݊����d�v���Ǝv���܂��B��N�̐V��������I�y�����C�������ł́A���̒����^�I�����̖����������̂ł����A���[�_�[�Ƃ��Ă̈Ќ���ӔC���ӎ������̏������Ă����Ǝv���܂��B����̖{�{�̖����̓��[�_�[�V�b�v�����ł͂Ȃ��A�s�����߂��悤�ȉ̏��B���ʂƂ��ă��h���[�k�̈ʒu�Â����s���m�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂����B
�@����ɑ��ă}�U�[�E�}���[�̖q��^�R���͑��݊����o���Ă����悤�Ɏv���܂��B���h���[�k�̗����ʒu���s���m�ȕ������}�U�[�E�}���[�̑��݊������������Ƃ������Ƃ�������܂���B�ł��悢�̏��ł����B
�@�O�Y�����̌�݁A���R�z��Y�̋R�m�A���J�����̎i�Ղ͂��ꂼ�ꎩ���̖�ڂ��ʂ����̂ɂ͏\���ȉ̏��ł����B
�@�o��l�����������߁A����̒��S�I�̎���W�߂ď㉉����̂���������悤�ł����A�܂����t�ɖ����U������܂������A�S�̂Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ��ǂ����t�������Ǝv���܂��B
�u�J��������C�����̑Θb�vTOP�ɖ߂�
�{�y�[�W�ŏ��ɖ߂�![]()
�ό����F2010�N2��17��
���ꗿ�FD���@6000�~�@5F2��9�ԁ@
����21�N�x�����|�p�U����⏕���i�|�p�n���������ʐ��i���Ɓj
2010�s���|�p�t�F�X�e�B�o���Q������
��ÁF���c�@�l���������/�Вc�@�l���{���t�A��
���������I�y���������
�I�y��3���@�����t������i�C�^���A��j�㉉
���F���f�B��ȁu�I�e���v�iOtello)
����F�E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A
��{�F�A���S�E�{�[�C�g
���F����������ّ�z�[��
�X�^�b�t
�w�@���@
�F�@
�@
���x���g�E���b�c�B���u���j���[�� 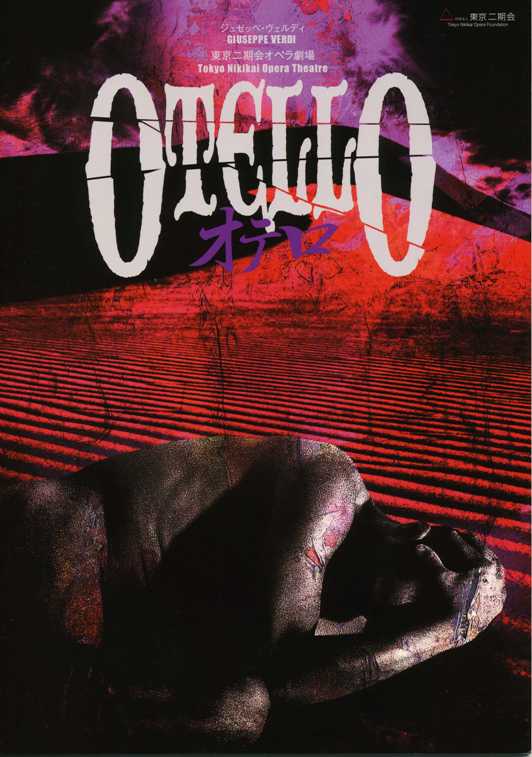
�I�[�P�X�g���@
�F�@
�����s�����y�c�@
���@���@
�F�@
�������c�@
�����w���@
�F�@
�����@�G�@
���@�o�@
�F�@
����@�W�@
���@�u�@
�F�@
����@��݁@
�Ɓ@���@
�F�@
�V���@�Βj�@
�߁@�ց@
�F�@
�O�c�@���q�@
����ē@
�F�@
���@���s�@
�o��
�I�e���@
�F�@
����@�h�@
�f�Y�f���[�i�@
�F
��R�@���I�q�@
�C�A�[�S�@
�F�@
�哇�@���Y�@
���h���B�[�R�@
�F�@
���S�@�a�L�@
�J�b�V�I�@
�F�@
�����@�[�O�@
�G�~�[���A
�F�@
���q�@�����@
���f���[�R�@
�F�@
�����@�p�s�@
�����^�[�m�@
�F�@
���с@�O��@
�`�߁@
�F
�{�R�@�q���@
���@�z�@����I�e���͕���Ȃ�-���������I�y������u�I�e���v��
�@����h���ŋߏd�߂̖����̂��Ă��邱�Ƃ͏��m���Ă���܂������A�{���������R�̐l�B�������������A�C�^���A�I�y���̑�\�I�ȃh���}�e�B�b�N�E�e�m�[�����ł���u�I�e���v���̂��B�m���ɂ��Ă̓e�m�[���̎�ɍׂ�����ʂ͂Ȃ��āA�Ⴆ�Γ����`�]�́A�A���}���B�[���@���݂�}���g���@������^���z�C�U�[�A���[�G���O���[���܂ʼn̂��Ă����킯�ł�����A���䂪�I�e�����̂��Ĉ������R�͂���܂���B�������A����̖{���̐����炷��A�I�e���Ƃ������̓J�b�V�I�ł��傤�B�����������䂪�ǂ������I�e���̕\��������̂��A�����������Ďf���܂����B
�@�����Ďv���̂́A�m���ɕ���h�̃I�e���ł����A�Ƃ������Ƃł��B����̕\���́A�e�m�[���E���u�X�g�̉̎肪�̂����ɒ������鈳�|�I�Ȕ��͂͂Ȃ��̂ł����A�����@�ׂŒ��J�ȉ̏��ł����B�{���̕���̐��͈̔͂ŁA�d�������o�����Ǝ��݁A�I�e���̉p�Y���Ɣj�ł��̂����킯�ł����A���ǂ̂Ƃ���A�p�Y�I�ȂƂ�������I�e���̎��i�ɂ����Ă���̃������R���b�N�ȕ\��ɕ���̗ǂ����o�Ă����Ǝv���܂��B����ɂ��Ă��I�e���Ƃ��Ă͌y�ʋ��ŁA���̒��ŏd���������o�����Ƃ��Ă��܂������A���S�ɂ��̃g�[�����ێ����邱�Ƃ͂ł����A���ł��Ȃ����V�^�e�B�[���H�̂Ƃ���ŋْ��������Ă��܂��āA�}���������Ȃ��Ȃ�Ƃ��낪����܂����B����ł��A�����͂������茈�߂Ă��܂����A�R��I�ȕ\���̂��܂��͗��ɕ���h�ƌ����ׂ��ŁA�y����Œ������Ƃ��ł��܂����B
�@�܂�����I�e���Ɠ����悤�ɖƐ����������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A�ǂ������̂��哇���Y�̃C���[�S�ł��B�哇�̉̏��͔�r�I�p�ɂɒ����Ă��܂����A����̃C���[�S�͏o�F�̏o���������Ǝv���܂��B�哇�̐��́A�o���g���E�u�������e�ƌ����܂����A�����������o���g���ŁA�C���[�S�Ƃ��Ă͌y�����̂悤�Ɏv���܂����B�C���[�S�̈�Ԃ̒������ǂ���ł���u�N���h�v�͐��R�Ɖ̂��āA�����ɍ��߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��C���[�S�̍��݂̗ʂ�����s�����Ă���悤�ɂ��v���܂������A����ȊO�ł��I�e���ɑ��鍦�݂̐[������������Ǝf����悤�ȉ̏��ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B�ǂ��炩�ƌ����Όy���ȃC���[�S�B
�@�������A�y�ʋ��̃I�e���Ƒg�ݍ��킳���ƁA���̌y���ȃC���[�S���▭�̃o�����X�ŁA���y�I���͂����o���Ă����܂��B�����������A��������������܂����B����̃I�e���ƃC���[�S�͊m���ɖ{���ł͂���܂��A���������s�����̃I�e���������ėǂ��Ǝv���܂��B
�@�X�ɁA���x���g�E���b�c�B���u���j���[���̎w���́A�d����������̂悳��Nj��������y���ł����āA���̐ꖡ����I�y���̌������������Ƃ����Ǝv���܂��B����I�P�E�s�b�g�ɓ������͓̂����s�����y�c�ł������A���͂̂���I�[�P�X�g�����������āA�w���҂̈Ӑ}��ꖡ�s���\�������Ǝv���܂��B���y��̉��F���ǂ��������ƁA�܂������n���̗������\���A�Ⴆ�A�e�B���p�j�̔����I�ȕ\���͑f���炵�����̂��������Ǝv���܂��B
�@�����������y�I�Ȑ�̂悳���d���������y�Â���ɂ́A����A�哇�̔�r�I�y���\�����ǂ��������܂��B���������_���܂߂āA�d���ł͂Ȃ�����ǂ����͓I�ȁu�I�e���v�ł����B
�@���o�͔���W�B�����݂̕��䑕�u�́A��艜���畑��O�Ɍ������Ă̎R�̐���̂悤�Ȃ��́B����̐�ւ��́A�݂艺����ꂽ�傫�ȃp�l����u���b�N�ł��B����̉��艜�ɂ̓X�N���[���������Ă���悤�ŁA���X����̉e���f��܂��B���ۓI�ŃV���v���ȕ���ł��B�����ŁA�̎肽�����̂�������̂ł����A���䂪�V���v���ł��邪�䂦�ɁA���ƌ��t�̖��͂������яオ�����悤�ł��B����́A���ۓI�ȕ���Ɏ��i�̈�������u�����Ƃɂ���āA�V�F�C�N�X�s�A���̖{�����l�ނ̕��Ղ̐^����˂��Ă���A�Ƃ������Ƃ��������������̂�������܂���B
�@�f�Y�f���[�i�̑�R���I�q�B���ł��B����̎�v�ȏo���҂̒��ŁA���Ɛ��Ƃ���Ԉ�v���Ă����̂����̕��ł��傤�B���̉̂���A���F�E�}���A�Ɏ���f�Y�f���i�̈�Ԃ̒������ǂ���͏�̂��ӂ��\���Ō��\�ł����B���̐�����f���炵���Ǝv���܂����B�������A����̃L���X�g�̒��ł́A�����d���������܂����B���ΓI�Ȃ��̂Ȃ̂ł����A����h�I�e���A�哇���Y�C���[�S�ł�����A�������������̉₩�ȃ\�v���m��I�����A�o�����X�I�ɂ͗ǂ������悤�ȋC���������܂��B
�@���̂ق��A�J�b�V�I���̂��������[�O��h���B�[�R���̂������S�a�L���Ȃ��Ȃ��ǂ��A�����̂��ƂȂ���������c���悩�����Ǝv���܂��B
�@���o�A���y�Â���A�����ĉ̏��ƃo�����X�̂Ƃꂽ�����䂾�Ǝv���܂����B�����̈ӗ~���ӂ�镑����ɔ���𑗂肽���Ǝv���܂��B
�@
�u�I�e���vTOP�ɖ߂�
�{�y�[�W�ŏ��ɖ߂�![]()
�ό����F2010�N2��18��
���ꗿ�FB���@5000�~�@2FBR1��36�ԁ@
����21�N�x�����|�p�U����⏕���i�|�p�n���������ʐ��i���Ɓj
2010�s���|�p�t�F�X�e�B�o���Q������
��ÁF���������̌���/�Вc�@�l���{���t�A��
���������̌���41����126��������
�ÓT����V���[�Y
�I�y��3���@�����t���̏�����i�C�^���A��j�䎌���{��㉉
���[�c�@���g��ȁu�U��̏���t�vK.196�iLa finta
giardiniera)
��{�F�W���[�b�y�E�y�g���Z�b���[�j�i�H�j
���F�I����z�[��
�X�^�b�t
�w�@���@
�F�@
�@
���B�[�g�E�N�������e 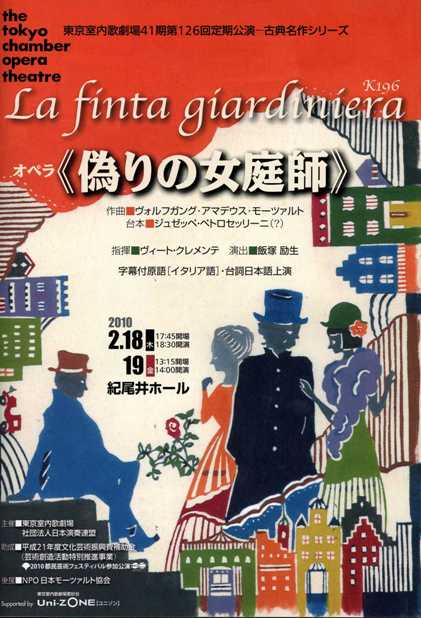
�I�[�P�X�g���@
�F�@
���������̌���nj��y�c�@
�ā@�C�@
�F�@
�C�V�V�@�q�@
�����A�h���@�C�U�[�@
�F�@
��@��q�@
���@�o�@
�F�@
�ђˁ@�㐶�@
���@�p�@
�F�@
���@���q�q�@
�Ɓ@���@
�F�@
���@���I�@
�߁@�ց@
�F�@
���I�@�ؑ�q�@
�U�@�t�@
�F
�唨�@�_�b�@
����ē@
�F�@
�[���@�B�@
�o��
�h���E�A���L�[�[�@
�F�@
�s�V�@�ˍW�@
����t�T���h���[�i�i��ݗߏ샔�B�I�����e�j�@
�F
���с@�ؔ��@
�x���t�B�I�[�����݁@
�F�@
�n�@�p�K�@
�A���~���_�@
�F�@
���}�@�����@
�R�m���~�[���@
�F�@
�����@�ߎq�@
�Z���x�b�^
�F�@
���g�@���q�@
�i���h�i���x���g�j�@
�F�@
�a�c�@�Ђł��@
�_���T�[�@
�F�@
���߁@�ꂨ�@
�_���T�[�@
�F
���܂��@
���@�z�@���[�c�@���g�̎Ꮡ��-���������̌���u�U��̏���t�v��
�@�u���[�c�@���g�ɂ͑ʍ삪�Ȃ��v�Ƃ����̂́A�N���V�b�N���y�t�@���ɂƂ��ċ^���Ă͂����Ȃ��e�[�[�ł����A�u�ʍ�v�����邩�ǂ����͕ʂƂ��āA���삪�ӔN�ɑ������Ƃ͕�����Ȃ������ł��B�O������Ȃ��A39�ԁA40�ԁA41�Ԃł����A�s�A�m���t�Ȃ�����20�Ԉȍ~�Ƃ���ȑO�ł͉��y�̐[�݂��Ⴂ�܂��B�I�y���ł��u�t�@�K���v�A�u�W�����@���j�v�A�u�R�W�v�̃_�E�|���e�O�����A�u���J�v�͐��l���Ă���̍�i�ł��B�P�b�w���ԍ���100�ԑ�̍�i�Ō���ƌĂ�ō����x���Ȃ��̂́A������25�Ԃ̏��g�Z���ƁA�f�B���F���e�B�����gK.136-138�����ł��傤�B
�@���[�c�@���g18�̂Ƃ��ɍ�Ȃ��ꂽ�h�����}�E�W���R�[�]�u�U��̏���t�v���A�܂����������̃h�^�o�^�쌀�ł����āA���̉��y�͑ʍ�Ɛ\���グ��ׂ������ł͂Ȃ��ɂ���A�_�E�|���e�O�����m���Ă���g���炷��A����ς�Ꮡ�����ȁA�Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B����̏㉉�ŁA���������̌���́A���V�^�e�B�[���H�E�Z�b�R�̕��������ׂē��{��̑䎌�ŏ㉉���܂������A�����Ă��̂悤�ɂ����̂́A�`�F���o���t�҂�������Ȃ��������߂ł͂Ȃ��A���V�^�e�B�[���H�����̂܂㉉����ƁA�璷�ɂȂ��Ă��܂��A�쌀�̖��킢���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ����뜜������������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�������A�䎌�����Ċ쌀�̖��킢�𑝂₷���������\���H�Ɛ\���グ��A����͂Ȃ��Ȃ�����Ƃ��낪����܂��B�n�p�K�ɂ���A���g���q�ɂ��悻��Ȃ�ɖʔ����̂ł����A�{���I�ɑf�l�|�ł��B�䎌�����͂͂�����\���グ��Ίw�|��ł����āA�����Ⴒ�������Ă��邤���ɂ��������̉��y�̎����킢����Ă��܂��B�O���ɕ������̂������́u�I�e���v�������킯�ł����A�u�I�e���v���ْ��̓r��Ȃ������䂾�������������āA�u�U��̏���t�v�̒o�ɂԂ�Ƃ��������U���A���ɒ��r���[�Ɋ����܂����B
�@���B�[�g�E�N�������e�̎w���A���������̌���nj��y�c�̉��t�͈������̂ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A�䎌�łԂԂƉ��y�̗��ꂪ��Ă��܂����ƂƁA���[�c�@���g�̉��y���̂�����̌���Q�Ɣ�r����ǂ����Ă���ۂ̔������y�ŁA��藧�ĂĐ\���q�ׂ�قǂ̃C���p�N�g�͊������܂���ł����B
�@�u�U��̏���t�v�́A�v����ɌÓT�I�ȃI�y���E�u�b�t�@�ŁA�o�b�\�E�u�b�t�H�ƃX�[�����b�g���d�v�ł����A�u�b�t�H�����A�e�m�[�����̃h���E�A���L�[�[�ƃo���g�����̃i���h�ɕ������Ă���̂��������Ǝv���܂��B�s�V�ˍW�̃h���E�A���L�[�[�̓h�^�o�^�̂Ȃ���|�M�����Ƃ��낪�ǂ��A�̂��y���Ŋy���߂܂����B�a�c�Ђł��̃i���h�́A�s�V�̃h���E�A���L�[�[�Ɣ�r����ƈꐡ�}�����\���������Ǝv���܂����A�B��̒ቹ�̎�Ƃ��ďd���̉�����������Ǝx���Ă����Ǝv���܂��B�܂��A���A���Ȃ��Ȃ��y���ł����B
�@�X�[�����b�g�̓Z���x�b�^�ŁA���g���q���̂��܂����B���g�̉̂͂Ȃ��Ȃ��f�G�Ȃ��̂ŁA���I�ɉ₩�ȃZ���x�b�^���\���\�����Ă����Ɛ\���グ�܂��傤�B�Ƃ���ŁA���̃Z���x�b�^�Ƃ������́A�u�t�B�K���̌����v�ɂ�����X�U���i��A�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�ɂ�����f�X�s�[�i�̂悤�ɕ���̗���ɖ{���I�ɓ��荞��ł�����ł͂Ȃ��A�ǂ��炩�ƌ����Εt�������̖��ŁA�����Ȃ�A���b�V�[�j�́u�Z�r���A�̗����t�v�ɂ�����x���^�̂悤�Ȋ����ł��B�Ƃ��낪�A�������������I�y���̍ō�����S���킯�ł�����A�Ȃ�Ƃ��o�����X���ǂ��Ȃ��B���������Ƃ��낪��L�̒��r���[���ɂȂ������̂�������܂���B
�@����̐n�p�K�Ə��эؔ��̃R���r�́A�n���܂��܂��ŏ��т�����ƌ����Ƃ���ł��傤�B�n�͂Ȃ��Ȃ������Y��ȃ����b�N�e�m�[���ŁA���[�c�@���g�̌y���ȕ\�������ɉ̂����Ǝv���܂��B����O����̏��эؔ��́A���܂�ς��Ƃ��܂���ł����B��Ԃ̒������ǂ���ł����̃A���A�u�c���Ȓj������v�͂�������Ƃ܂Ƃߏグ�܂������A���ɍ���͂����肸�A�^�C�g���E���[���Ƃ��ẴI�[�����������܂���ł����B
�@���}�����̃A���~���_�̓T���h���[�i�̓G���Ƃ��đ��݊��\���A�܂������ߎq�̋R�m������ɂ܂Ƃ߂Ă����Ǝv���܂��B
�@�ȏ�A�ʂɌ��Ă�������ȂɈ��������͂��Ȃ��̂ł����A��i���̂̎コ�ƁA�g�ݍ��킳�ꂽ���̃x�N�g���̔����Ȃ��ꂪ�A�S�̂Ƃ��Ă͉��y�I�Ȕ��U�ɂȂ���A���r���[�ȏ㉉�ŏI������悤�ȋC�����܂��B�Ȃ��Ȃ��㉉����Ȃ���i�́A���ꂾ���̗��R������悤�Ɏv���܂����B�@
�@
�u�U��̏���t�vTOP�ɖ߂�
�{�y�[�W�ŏ��ɖ߂�![]()
�ό����F2010�N2��23��
���ꗿ�FC�ȁ@7560�~�A�S�e�@2��39��
��ÁF�V��������
�I�y��3���@�����t������i�h�C�c��j�㉉
���[�O�i�[����j�[�x�����O�̎w��2���u�W�[�N�t���[�g��iSiegfried)
��{�F���q�����g�E���[�O�i�[
���@�V��������E�I�y������
�X�^�b�t
�w�@���@
�F�@
�@
�_���E�G�b�e�B���K�[ 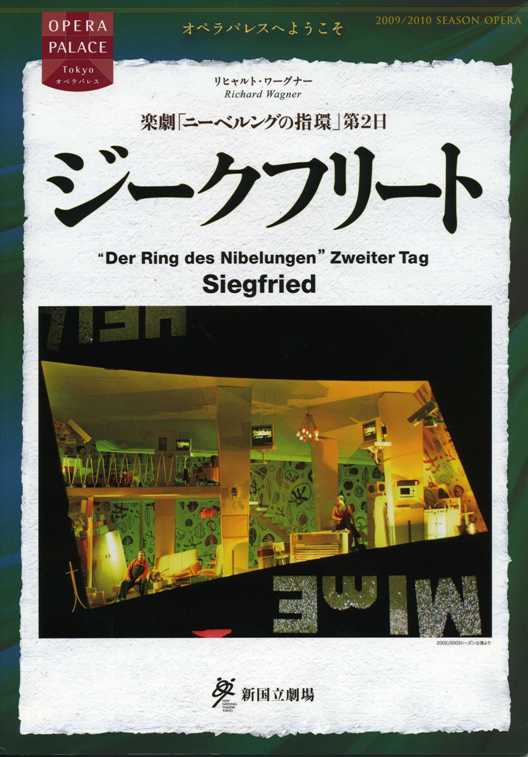
�I�[�P�X�g���@
�F�@
�����t�B���n�[���j�[�����y�c�@
���@�o�@
�F�@
�L�[�X�E�E�H�[�i�[
���u�E�ߏց@
�F�@
�f���B�b�h�E�t�B�[���f�B���O
�Ɓ@���@
�F�@
���H���t�K���O�E�Q�b�y��
�U�@�t
�F�@
�N���A�E�O���X�L���@
���y�w�b�h�R�[�`�@
�F
��@�G�@
����ē@
�F�@
��m�c�@��F�@
�o��
| �W�[�N�t���[�g | �F | �N���X�`�����E�t�����c |
| �~�[�� | �F | ���H���t�K���O�E�V���~�b�g |
| �����炢�l | �F | ���b�J�E���W���C�l�� |
| �A���x���q | �F | �����Q���E���� |
| �t�@�t�i�[ | �F | �ȉ��@�G�a |
| �G���_ | �F | �V���[�l�E�V�����[�_�[ |
| �u�������q���f | �F | �C���[�l�E�e�I���� |
| �X�̏��� | �F | ����@�z�q |
���@�z�@���H�l��̃I�y��-�V��������u�W�[�N�t���[�g�v��
�@�_���E�G�b�e�B���K�[�A���ɂȂ����ȁB�|���l�Ȃ��ɂ����v���܂��B�̂��炻��Ȃɉ���Ȏw���҂ƌ�����ۂ͂Ȃ������̂ł����A��N�́u�����L���[���v����X�ɐi��������ۂł��B�v���~�G�������̏��E�����N��/NHK�����y�c�̃R���r�Ɣ�r����ƁA���y�̍\�}�����������܂�������炴��Ȃ����̂�����܂����A�G�b�e�B���K�[�̎w���̐ꖡ�́A�������x���������Ɛ\���グ�Ă悢�Ǝv���܂����B�����t�B�������ꂾ���v��������炳���Ă���̂ł�����A�u�w�v�̉��y�ɑ���ӎ������Ȃ薾�m�ɂȂ��Ă���̂��낤�Ǝv���܂��B
�@�����t�B�����S�̓I�ɂ̓f���i�[�~�N��傫���Ƃ����X�P�[���̑傫�����t�ŗǂ������Ǝv���܂��B�����A���Ɍ㔼�̓~�X���ڗ����Ă���܂����B�z�����Ƃ��ł��ˁB���ꂾ���̒����ԉ��t����̂ł�����A�㔼���Ă���̂͂�ނȂ��̂ł����A��O���͌��\������������ۂł��B����ł��g�[�^���Ō���A���Ȃ�D�G�ȉ��t�������Ǝv���܂��B�V��������̃I�P�s�b�g�ɓ��������̓��t�B���́A���\�ᔻ����邱�Ƃ������̂ł����A���炢�����ꏊ�����ɉ��t���Ă���������A���������ᔻ�͐������邾�낤�ȁA�Ǝv���܂����B
�u�W�[�N�t���g�v����ɂ��Ă���ςȃI�y���ł��B�㉉���Ԃ�����4���Ԕ��B�ɂ�������炸�A�o���҂����Ȃ��B�킸��8�l�B���̂����X�̏�����t�@�[�t�i�[�A�A���x���q�Ȃǂ͂���Ȃɒ����ԏo��킯�ł͂���܂���A�t�Ɍ����A�W�[�N�t���[�g�A�~�[�l�A�����炢�l�Ȃǂ̕��S�͔��ɑ傫���ł��B�����āA���[�O�i�[�̊y���͑�Ґ��̃I�[�P�X�g���ɕ����Ȃ���������v�������킯�ł�����A�����ԋ������ʼn̂�������̗͂̎�����łȂ���A����̂����Ȃ��܂���B�v���U��Œ����āA�w���H�l��̃I�y���x���ȁA�Ǝv���܂����B���H�j�q�����s���̓��{�l�ł͉̂����Ȃ��Ȃ��͎̂d�����Ȃ��̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂��܂��B
�@���ꂾ���ŁA��v�����̂����̎�̗͂�����܂��B
�@�W�[�N�t���[�g���̂����N���X�`�����E�t�����c�A�ǂ������ł��B�ނ́A���̕���v���~�G�̎����������ăW�[�N�t���[�g���̂��A��ϊ��S�������Ȃ̂ł����A���̎��̈�ۂ��܂��v���o���̏��ł����B���́A�����ނ��w�����ɓ������������Ĕ������A����ł��đS�̂Ƃ��Ă͐[�݂Ɨ͋��������˔����Ă���A�w���f���e�m�[���Ƃ��Ă̔��_������������Ǝv���܂��x�ƕ]�����̂ł����A���̈�ۂ͍�����ς��܂���ł����B�͋����w���f���E�e�m�[���ł���Ȃ���A�_�炩���������������o����Ƃ����̂͑傫�Ȗ��͂��Ǝv���܂��B��́u�X�̂����₫�v�̕����̑@�ׂȕ\���́A���������t�����c�̈�Ԗ��͓I�ȕ������������悤�Ɏv���܂����B�����āA��O���̃u�������q���f�Ƃ̈��̓�d���B�ǂ������ł��B�O����Ƀt�����c�������Ă������ƁA��ό��\�Ȑl�I�ł����B
�@�~�[���̃E�H���t�K���O�E�V���~�b�g���ǂ������ł��B�~�[���ƌ����͋������o���Ȃ���ڋ������\�����Ȃ�������Ȃ����A�Ȃ�Ƃ��R�~�J���ɉ̂����Ǝv���܂��B�Ƃ������̎��͕̂ʂɃR�~�J���ł͂Ȃ������̂ł����A�~�[�����j�[�x�����O���̏��l�ł��邱�Ƃ܂��������̓R�~�J���ŁA�L�����N�^�[�E�e�m�[���̖��킢����������o���Ă����Ǝv���܂��B�V���~�b�g�̓W�[�N�t���[�g���������Ȃ̂������ł����A���̃j�[���̓����Ɖ̏������Ă���ƁA�W�[�N�t���[�g���z���ł����A��x�ނ̃W�[�N�t���[�g�������Ă݂������̂��Ǝv���܂����B�@
�@�����炢�l���̂������W���C�l���̓e�m�[����l�ɗ�炸���h�ȉ̏��������Ǝv���܂��B���W���C�l�����v���~�G���̂����炢�l�ŁA���̕���̈�ۂ��܂��c���Ă���̂ł��傤�ˁB���݊��̋��������炢�l�������悤�Ɏv���܂��B1���̃~�[���Ƃ̊m���̕����ł̗͋����Ƃ��ǂ남�ǂ낵���A�j���̃A���x���q�Ƃ̑Ό��A�O���̃G���_�Ƃ̊��ݍ���Ȃ��Θb�A�ǂ̕������A�v���~�G�����������������L�т₩�ȉ̏��ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B���W���C�l���̉̏��́A�v���~�G�������ǂ��Ȃ��Ă���悤�Ɏv���܂����B
�@�����̃A���x���q�B���\���݊�������܂����B��ɂ����邳���炢�l��~�[���Ƃ̓�d���́A�A���x���q�̍��߂�ꂽ���݂�������������̂ŗǂ������Ǝv���܂����B�t�@�t�i�[�̍ȉ��G�a�B�d�ʋ��̉̎�̊ԂŌ������Ă����Ǝv���܂��B
�@�����w�͒j���Ɍނ��Ċ撣���Ă��܂����B���ɃC���[�l�E�e�I�����̃u�������q���f�B���̗����オ�肪�����Ɖ��₩���Ə��悢�Ǝv���܂����B�h���}�e�B�b�N�E�\�v���m���������āA�͋����̏��͗��Ȃ̂ł����A�\�������d���A�������Ɨ�����������Ȃ��悤�ȂƂ��낪����Ǝv���܂����B�����̂��̖̂��͂́A�t�����c�̃W�[�N�t���[�g�Ɣ�ׂ�ƈꐡ�����銴�����������܂�������ȂɈ����Ȃ��Ǝv���܂����B
�@�G���_�̃V���[�l�E�V�����[�_�[�B���̕����d�v�Ȗ����Ȃ̂ł����A����ڗ����Ȃ������悤�Ɏv���܂����B�܂�����z�q�̐X�̏����B����̎Ⴓ�Ɣ����������ƂŊ撣���Ă����Ǝv���܂��B�������\���Ǝv���܂����B
�@�ȏ����̂悤�ɋx�e�������6���ԁA��������Ɗy����ł܂���܂����B���[�O�i�[�L���̖�����y����Œ��������ƁB�悩�����Ǝv���܂��B
��W�[�N�t���[�gTOP�ɖ߂�v
�{�y�[�WTOP�ɖ߂�
![]()
�ӏܓ��F2010�N3��5��
���ꗿ�F1500�~�@����28��
�������y��w�~�T���g���[�z�[���@�I�y���E�A�J�f�~�[���ʌ���
��ÁF�������y��w
���́F�T���g���[�z�[��
�I�y��2���A�����t����i�C�^���A��j�㉉
���[�c�@���g��ȁu�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�K.588�iCosì fan
tutte)
��{�F�������c�H�E�_�E�|���e
���F�������y��w�u��
�X�^�b�t
| �w��/�`�F���o�� | �F | �W���[�b�y�E�t�B���` |
|
| �nj��y | �F | �������y��w�I�[�P�X�g�� | |
| ���@�� | �F | �������y��w�����c | |
| �t�H���e�s�A�m | �F | �j�R���E���C�]�b�e�B | |
| �o���b�N�E�`�F���@ | �F�@ | ���c�@�M�k | |
| �e�B�I���o�@ | �F�@ | �����@���I�q�@ | |
| ���@�o | �F | �K�u���G�[���E�����B�A/�c���@���q | |
| �Ɓ@�� | �F | �쑽���@�M | |
| ����ē� | �F | �[���@�B |
�o�@��
| �t�B�I���e�B���[�W | �F | �����@���S�� |
| �h���x�b�� | �F | ����@�a�̎q |
| �t�F�����h | �F | �N�c�@�� |
| �O���G���� | �F | �܉́@�G�� |
| �f�X�s�[�i | �F | �h���@���� |
| �h���E�A���t�H���\ | �F | �����@�p�� |
�i�r�Q�[�^�[�F�E�R�@��
���z�@���ڂQ���[�g��-�������y��w�~�T���g���[�z�[���@�I�y���E�A�J�f�~�[���ʌ����u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v���B
�@�{�N3��14�����T���g���[�z�[���Ńz�[���E�I�y���u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�����t�����̂ł����A���̗��K�ꏊ��������ŁA�������y��w�u���Ńv���������s���܂����B�������A�{�����ł͊O���l�̎肪�̂��̂ł����A����̓I�y���E�A�J�f�~�[�ŕ����́A�{�����ł̓J���@�[�ɉ������{�l�̎肪�o�����A�I�[�P�X�g�������������y�c�ł͂Ȃ���������̃I�[�P�X�g���B�����͖{�����ł��̂���������̍����c�i���A�{�����ł́u�T���g���[�z�[���@�I�y���E�A�J�f�~�[�v�Ƃ������̂ɂȂ�܂��j�B�܂��{�����Ŏw�������Ȃ���t�H���e�s�A�m�Ń��V�^�e�B�[���H�̔��t�����郋�C�]�b�e�B�̓t�H���e�s�A�m�̉��t�݂̂ɂ܂��A�w���͕��w���̃t�B���`�������܂����B
�@��������u���̕�����g���Ă̏㉉�ł����A�z�[���E�I�y���`���Ƃ������ƂŁA���͉���邱�Ƃ�����܂��A�I�[�P�X�g�����s�b�g�ɓ���̂ł͂Ȃ��ĕ���̏�ɂ��܂��B�������A�ʏ�̃I�[�P�X�g�������Ƃ͈Ⴄ�̂́A�I�[�P�X�g���͕��䉜�Ɉʒu���A����̕ǂɌ������ĉ��t���邱�Ƃł��B�w���҂͋t�ɋq�ȑ��������Ă��邱�Ƃł��B���Ȃ݂ɁA�̎�͎w���҂������Ȃ��̂ŁA���䑳��q�Ȃɉ�����̃��j�^�[���u���Ă����āA���̃��j�^�[�ɉf���Ă���w���҂̎w�������Ȃ���̂������ł��B
�@����������@���Ƃ����̂́A�I�[�P�X�g�����s�b�g���ł����t��`���̃I�y���㉉���ƁA�ǂ����Ă��I�[�P�X�g���̉��������Ȃ肷���āA�̎�̐��̃j���A���X���͂����肵�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���Ƃ�ꂽ�A�C�f�B�A�������ł����A����́A���������Ƃ����Ƃ���ł��傤�B�m���ɁA���͈�x�ǂɂԂ����ċ����̂ŁA�S�̂ɃI�[�P�X�g���̉������_�炩���Ȃ���ʂ͂���܂��B�������A���Ƃ��Ƃ̃I�[�P�X�g���̋Z�ʂ����܂荂���Ȃ��̂ŁA���̉��̓����x���Ⴍ�A�����������������荇�����Ƃɂ���ĉ��̗֊s�������Ă��܂��ڂ��肷��B�ڂ��肷�邾���Ȃ疢�������̂ł����A�ꍇ�ɂ���Ă͑����Ă��܂��Ƃ����Ƃ��낪����܂����B�v���̃I�[�P�X�g���ł�������Ɨǂ����ʂ��o��̂ł��傤���A�w���I�[�P�X�g���̋Z�ʂł́A�K���������̌��ʂ������o���Ȃ������悤�Ɏv���܂����B
�@���o�́A�{�����̉��o�Ƃł��郉���B�A�̃A�C�f�B�A��c�����q����̉��������̂������ł��B����]�����̉��y�̓r����Ȃ������߂ɁA���q�����y�̂Ȃ��Ă���Ԃɕ�����ǂ�ǂ�ς��Ă��܂��B��{�I�ɑ哹��͂Ȃ��A�֎q��x�b�h�A�e�[�u���Ȃǂ���������ŁA�������荞��ł����܂��B�g�p�����Ƌ�ނ́A�A���b�T���h���E�J�����̂��̂ŁA�S���قłł������̂ł��B���q�́A�C�^���A�̓`�����w�R���f�B�A�E�f�����e�x�ɓo�ꂷ��u�v���`�l�b���v���C���[�W�����ߑ������Ă��܂��B�����h�@������Ƃ��鍕���}�X�N�����A�����ߏւœo�ꂵ�܂��B
���Ȃ݂ɍ����c�������ߏցB���q�ƍ����c����ʂ���̂̓}�X�N�̂���Ȃ��ł����B
�@�Ƃ���ŁA���i���̓I�y����V��V�~�Œ������Ƃ������̂ł����A����͂������`�P�b�g�������A�Ƃ������Ƃ�����̂ł����A����ȏ�ɑS�̂����n����Ƃ��낪�C�ɓ����Ă��܂��B�܂����䂩�牓���̂ŁA�̎�̗͗ʂ��������₷���Ƃ����Ƃ��������܂��B�������A���䂩�牓���Ƃǂ����Ă��ׂ����Ƃ���͂����܂��ɂȂ�܂����i���y�I�ɂ͂��̕����ǂ����Ƃ������̂ł����j�A�ׂ��ȋZ�p�I�ȕ����͂悭�������Ȃ����Ƃ������̂ł��B
�@�Ƃ��낪�A����͋��R1��ڂɍ��邱�ƂɂȂ�A�܂�����̓I�[�P�X�g���E�s�b�g���݂����Ă��Ȃ��̂ŁA��ԋ߂��Ǝ��Ƃق�2���[�g����������Ă��Ȃ��Ƃ���ŁA�̎肽�����̂��̂ł��B�����Ȃ�ƁA���i�����Ȃ��Ƃ��낪�����Ă��܂��B�Ⴆ�A�d���ɂ����ĒN���ǂ�ȉ����ʼn����̂��Ă��邩�����S�ɕ�����܂��B�Ⴆ�Ε��ʒj���O�d���œ����̎����̂����A�o�X��o���g���̃����f�B�[���ǂ���̉̎肪�̂��Ă��邩�ȂǂƂ������Ƃ́A���̐Ȃł͑S��������Ȃ��̂ł����A���ڂ��Ƃ������������Ă��܂��̂ł��B���������������Ă���ƌ����Ă�����̂�����܂����B���Z�����l�ł��B�ׂ�����̎g������\��ȂNJ����Ɍ����Ă��܂��܂��B�ׂ������o�́u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�v�炵���A���E�Ώ̐����d���������̂������̂ł����A�̎肽���̉��Z�����Ă���ƁA�����ׂ��ȂƂ���܂Ŏw���������Ă���悤�Ɏv���܂����B
�@����ł����ڂ͂��܂�ǂ��Ȃ��ł��ˁB�ǂ����Ă��������̏����ł����܂��B���C�]�b�e�B���t�H���e�s�A�m�Ń��V�^�e�B�[���H�E�Z�b�R�̔��t��������A��������q�������[�g�̐e���̂悤�ȃe�B�I���o�����t������A�o���b�N�`�F���ɂ��ʑt�ቹ�I���t�������Ă���̂ł����A���̌��ʂ̉��̖c��݂͂��̈ʒu�ł͂͂����芴���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�܂��A���͕������ĕ���������~�b�N�X���Ē�����������ǂ����Ƃ������̂ł��B�S�̓I�Ƀs�V�b�Ƃ�����ۂɂȂ�Ȃ������̂́A�Ȃ̊W���傫���悤�ɂ��v���܂����B
�@���ĉ��t�S�̂̈�ۂł����A��{�I�ȉ̏��Z�p�͍����A�悭�܂Ƃ܂��Ă��舫�����̂ł͂���܂���ł������A�S�̓I�ɐ��^�ʖڂȈ�ۂ������A�u�R�W�v�Ƃ�����i�������Ă���{���I�Ȃ������݂��o�������t�ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B
�@�܂���ԋC�ɂȂ�̂��A�h���E�A���t�H���]�ƃO���G�����ł��B����A�h���E�A���t�H���\���p�炪�A�O���G������܉͍G���������܂������A����͋t�ɂ��ׂ��������Ǝv���܂��B���c�͐��̋������y���A�����ɖ��͂�����܂��B����A�܉͂͒ቹ�����ǂ��������ɐ[�݂�����܂��B���̓������猾���A���c���O���G�����Ɍ����Ă��܂����A�܉͂��A���t�H���\�Ɍ����Ă���B���ۂ̉̏����Ă��Ă��A�܉͂͋������Ⴍ�Ȃ肪���ŁA�O���G�����̎�X�������K�v�ȕ����łǂ�����Ƃ������������̂悤�Ȃ��̂��������Čy�������s�����Ă��܂������A���c�͋t�ɉ̏����y���Ȋ����ɂȂ��āA�N�w�ғI���͋C���ł����B�X�ɐ\���グ��A�����̎����̂��d�������ł́A�܉͂��ቹ���c�����������̂��Ă��邱�Ƃ�����A���{�l���������̕ӂ̃M���b�v�͋C�t���Ă����悤�ł��B�ǂ������������ł��̂悤�ȃL���X�e�B���O�ɂȂ����̂�������܂��A���Đ܉͂̂Ȃ��Ȃ��s���A���t�H���\�Ɋ��S�������Ƃ̂��鎄�Ƃ��ẮA�c�O�łȂ�܂���B
�@�e�m�[���̟N�c���̃t�F�����h�͂��̖��ɂ悭�����Ă��܂��B�N�c�̂悤�ȃ��W�F�[���n�̐������t�F�����h�ɂ҂�����ł��B�������A���Ē����Ċ��S�������قǐ��̓��������Ȃ��悤�Ɏv���܂����B������s���������̂��A����Ƃ��N��I�Ȗ��Ȃ̂�������܂���B�̗̂l�����̂悤�Ȃ��̂͂������肵�Ă�����Ȃ̂ŁA���̓����x�s�����旳�_�˂������Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�܂���ł����B
�@�������S���̃t�B�I���f�B���[�W�͐L�т₩��������Ȃ��悤�Ɏv���܂����B�قڂ�������Ɖ̂��Ď茘���܂Ƃ߂Ă͂���̂ł����A����ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B���S�̂ɕ\��d���A����̂ɏ���Ă��Ȃ����炢������܂��B�h���x�b�����̏���a�̎q�����ɕ\��L���ŁA���l�ƈꏏ�ɂ���Ƃ��̊y����������A�߂����A�����Ȃǂ��炢���ς��ɑ̌����Ă���̂ɁA�����͂������Ȃ��āA�]�T���Ȃ������悤�ł��B�������Z�p�I�ɂ��u��̂悤�ɓ������v�ɂ����鉺�~����̂悤�ɂ�������ƌ��܂�Ȃ��Ƃ���͂������̂ł����A�v���}�E�h���i�̃I�[���������Ȃ��Ƃ��낪����ȏ�Ɏc�O�ł����B
�@����a�̎q�̃h���x�b���͂悩�����Ǝv���܂��B���J�Ȗ����ł������A�̏������J�ł�������ƌ��߂Ă��܂����B�h���x�b���͓��ɑ�͊쌀�I�ȕ\���������Ȃ�킯�ł����A���̎��̃R�~�J���ȓ�����\��L���Ŋ���ǂ�������Ƃ�����悢�Ǝv���܂����B
�@�h�����߂̃f�X�s�[�i���ǍD�ł��B�����Ƃ��Ẳ��Z���ʔ����A�܂��y���ȉ̏������\�B�u�j��R�l�ɒ�߂������]�݂ł����H�v���u����15�ɂȂ�v���Ɍy���ɉ̂��܂������A��̈�҂���ؐl�ɉ������Ƃ��̉̏��������Ȃ��B�h���̖������ƕ\��ɗV�т��Ȃ����ƂŁA�f�X�s�[�i���������������̂��Ƃ����\����o���X�ɖʔ����Ǝv���܂����B
�u�R�W�E�t�@���E�g�D�b�e�vTOP�ɖ߂�
�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()
�ӏܓ��F2010�N3��11��
���ꗿ�F2700�~�@2F3��38��
�V��������I�y�����C������
��ÁF�V��������
�I�y��3���A�����t����i�C�^���A��j�㉉
���F���f�B��ȁu�t�@���X�^�b�t��iFa��staff)
��{�F�A�b���[�S�E�{�[�C�g
���F�V�������ꒆ����
�X�^�b�t
| �w��/���y�w�� | �F | �A���E�x���g |
|
| �nj��y | �F | �����V�e�B�E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c | |
| ���@�� | �F | �����̌��c������ | |
| ���o/���Z�w�� | �F | �f�B���B�b�h�E�G�h���[�Y | |
| ���p�E�ߑ��@ | �F�@ | �R�����E���C�Y | |
| �Ɓ@���@ | �F�@ | ����@��O�@ | |
| ����ē� | �F | ����@�~�� | |
| �w�b�h�E�R�[�` | �F | �u���C�A���E�}�X�_ | |
| �����w�� | �F | �����@���� |
�o�@��
| �t�@���X�^�b�t | �F | ���@�p�a |
| �t�H�[�h | �F | ��c�@�q�� |
| �t�F���g�� | �F | ����@�C�� |
| ��t�J�C�E�X | �F | �Z���W���E�x���g�b�L |
| �o���h���t�H | �F | ����@���� |
| �s�X�g�[�� | �F | �㓡�@�t�n |
| �A���[�`�F�@ | �F�@ | �����@�^�I�@ |
| �i���l�b�^�@�@�@�@�@�@ | �F�@ | �ؑ��@�����q�@ |
| �N�C�b�N���[�v�l�@ | �F�@ | �����@�߂��� |
| �y�[�W�v�l�E���O�@ | �F�@ | ���c�@�퐶�@ |
| �K�[�^�[���̎�l�@ | �F | �����@�\�s�@ |
| �@ | �@ | �@ |
���z�@�V�l�������V�l-�V��������I�y�����C�������u�t�@���X�^�b�t�v���B
�@�t�@���X�^�b�t�̎������̂͑���8�x�ڂ��Ǝv���܂����A�������тɌ��삾�ȁA�Ƃ̎v����V���ɂ��܂��B�X�g�[���[�͖ʔ������A���y�I�Ȗ��ʂ͂Ȃ��B�`���́uFalstaff,�@Sir
John
Falstaff�v�ƈ�t�J�C�E�X�ɂ���ĉ̂��n�߂��镔������A�Ō�́u���̒��F��k�v�Ɖ̂���d�������܂Œ����Ă��Ă����Ԃ�y������i�ł��B�������A�����͘V���ȃ��F���f�B�̍�i�A�����ȒP�Ɉ�ؓ�ł�����i�ł͂���܂���B���̈Ӗ��ŃI�y�����C�������グ��ɂ͂��Ɖׂ��d���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂����B
�@�m���ɃA���T���u���E�I�y���̑��ʂŌ��Ă�����ł����A�V��������I�y�����C���Ƃ��Ă͎��グ�Ă݂�����i���낤�Ƃ������Ƃ͂킩��̂ł����A�Ⴂ�l�������̂��Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��������m���ɂ���̂ł��B�������Ԏv�����̂́A�^�C�g�����̉̏��ł��B
�@���p�a�́A�u���]������̔����ł����A�v���v���̚�����������������肵���̏��ł����B�A���T���u���̃��[�h��������ɂ��Ȃ��Ă��܂����B��3���`���́u���E���D�_���v�Ȃǂ��ƁA���h���ȁA�Ǝv���܂����B�ł����̉̏��E���Z�ł̓t�@���X�^�b�t�̖��͂�`������Ă��Ȃ��B�ꌾ�ł����A���̏�����D�u�Ƃ��߂��Ă���̂ł��B�{���A�t�@���X�^�b�t�͎��M�ߏ�̂ӂ�����������}�ł��B���ۂ͎����̘V�����C���t���Ă��܂����A���ɂ��Ă邩�ǂ��������āA�ꖕ�̕s��������̂ł͂Ȃ����B���̍�i���������ꂽ���A���F���f�B��80�˂ł��B���F���f�B�́A���V�̊Ⴉ�猩���V�l�̔߂��݁A���������������y�ɂ��Ă��܂��B�t�@���X�^�b�t�͏������������ǂ��A������ނ����グ���j�R���C�́u�E�B���U�[�̗z�C�ȏ��[�����v�Ɣ�r���āA�t�@���X�^�b�t�ɑ��鉹�y�I�������D����������̂́A�V�l�̊�Ńt�@���X�^�b�t�ƌ����L�����N�^�[�����Ă��邹���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����������Ƃ��̂≉�Z�ŕ\�����邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă�������x�̃L�����A��o�����K�v�ɂȂ�A�Ⴂ�̎肪�m���Ƃ��Ēm���Ă��āA����Ȃ�Ɏ������i�D�ʼn̂����Ƃ���ŁA�g�ɒ����Ȃ��Ƃ��낪����A��a���������Ă��܂��̂ł��B���̉̏��͑������h�Ȃ��̂ł����̂ŁA���̈�a�����t�ɃN���[�Y�A�b�v����Ă��܂����������������܂����B
�@��c�q�͂̃t�H�[�h�����`������͂����肵�Ȃ����̂ł����B�t�H�[�h�̓t�@���X�^�b�t�Ɠ����o���g���Ȃ���A�̏��ł��̑Η������������茩���Ȃ�������Ȃ�������ł��B�����Ȃ���|���b���ɑ���h���E�W�����@���j�ł��B�����t�@���X�^�b�t�ƃt�H�[�h�́A�h���E�W�����@���j�ƃ��|���b���Ƃ̊W�Ǝ��e�����t�]���Ă���̂ŁA��藧���ʒu������̂ł��B��c�̉̏��́A�t�@���X�^�b�t�Ƃ̑Η����������Ƃ����ϓ_�ł́A�قƂ�lj��̍l�����Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�t�H�[�h�̈�Ԃ̒������ǂ���ł���u���������v�͌��\��������Ɨ����Ă��܂����悤�Ɏv���܂����B
�@�����^�I�̃A���[�`�F������B�ޏ��́A��N�́u�J��������C�����̑Θb�v�ł̃��h���[�k�C���@���̉̏����ƂĂ��悩�����̂Ŋ��҂��Ă����̂ł����A���҂͂��ꂾ�����Ɛ\���グ����Ȃ��B�����̐L�т�����ŁA����ɉ̂��ɕςȕȂ������āA��������ƓZ�܂�Ȃ���ۂł����B�N�C�b�N���[�v�l�̉���߂��݂́A�����ƃP��������\�ɏo�����̂����ł������ق����A�N�C�b�N���[�̑��݊����o���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�悩�����͎̂���C���t�F���g���Ɩؑ������q�B���������̔N��ƈ�ԋ߂����l�����̉̏��ł�����A���ꂮ�炢�̂��Ă����Ȃ��ƍ���̂ł����A����ɂ��Ă����͐L�тĂ������A���S���Ē����܂����B
�@����ȊO�̘e��w�͂����ނ˗ǍD�B�V��������̖{�����ł����̖����̂��Ă��鑝�c�퐶�̃��O�͗��̗͗ʁB�{�����ł͑��c�͂��܂�ڗ����Ă��Ȃ������Ǝv���̂ł����A���C�������Ƃ��Ȃ�ƁA��y�Ƃ��ď����A���T���u�������������Ă��܂����B��������̃o���h���t�H���������葶�݊����o���Ă��܂����B�㓡�t�n�̃s�X�g�[����������݂��͂����肵�Ă��Ȃ������̂Ɣ�r����ƁA�o���̍��͑傫���̂ł��傤�B
�@�f�B���B�b�h�E�G�h���[�Y�̉��o�́A�����1960�N��̃E�B���U�[�Ɉڂ����Ƃ����ǂݑւ��ŁA������p�͓������ӎ������T�C�P�f���b�N���ł����B�����āA�E�B���U�[�̎s���Ƃ������ƂŁA�V�������ꉉ�����C���̃����o�[���^���o�����Ă��܂����B�������A�ނ�͕s�v�ȑ��݂ł����B�����Ɛ\���グ��A�قƂ�ǎז��Ɛ\���グ�Ă悢�B���p�I�ɂ������������Ȃ��A�X�ɈӖ��̂͂����肵�Ȃ��l��������R����̂́A�����������F���f�B�̑f���炵�����y�ɐZ�肽�����ɂƂ��ẮA���炿��Ɩڏ��ł����B
�@�A���E�x���g�̉��y�Â�������o���p�ƌĉ������̂��A���Ɖs�p�I�ȉ��t�ŁA�I�[�P�X�g�����悭�Ȃ炵�܂��B�u�t�@���X�^�b�t�v�̓V���t�H�j�b�N�ȕ\�����\�ȃI�y����i�Ƃ��ėL���ŁA���������������߂���{�I�ɂ͍D���Ȃ̂ł����A�ꐡ�I�[�P�X�g�����O�ɏo�߂�����ۂł��B�I�[�P�X�g���̉��̃J�[�e���ɉ̎肽���̐��������B�ꂵ�Ă���Ƃ��낪����A��������������������悤�ɂ��Ă���������A���Ɍ����A�̎肽���̓I�[�P�X�g���ɕ����Ȃ��悤�ɐ������Ă���������悢�̂ɂȂ��A�Ǝv���܂����B
�u�t�@���X�^�b�t�vTOP�ɖ߂�
�{�y�[�WTOP�ɖ߂�![]()
![]()
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
